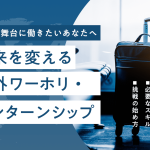ホテル客室のインスペクションは、清掃後の状態を最終確認する重要な工程です。清掃ミスを防ぎ、品質を安定させるためにも、チェック基準を整理したマニュアルの整備は欠かせません。この記事では、インスペクションマニュアルの具体例や部位別のチェックポイントを紹介しながら、現場で役立つマニュアルの作り方や、外国籍スタッフにも伝わる工夫まで詳しく解説します。
ホテル客室のインスペクションにマニュアルが必要な理由
客室清掃が終わったあと、仕上がりを最終確認するインスペクション。この工程があることで、清掃品質を安定させ、見落としを防ぐことができます。
ここでは、インスペクションマニュアルがなぜ必要なのか、その理由と効果について解説します。
インスペクションは清掃後の最後の品質チェック
インスペクションとは、清掃が完了した客室の状態を最終確認する工程のことです。
髪の毛の残りや備品の補充漏れ、水回りの水滴跡など、細かい部分まで厳しくチェックします。
お客様をお迎えする直前のこのチェックが、清掃品質を一定に保つ大切な最終確認となります。
清掃ミスが起きる原因と見落としやすいチェックポイント
どれだけ真面目に作業していても、清掃ミスや確認漏れは起きてしまうものです。
その原因の多くは、「作業を急ぎすぎる」「覚える項目が多すぎる」「チェックの視点が固定されている」といった状況から生まれます。
特に見落としやすいポイントとしては、たとえば以下のような箇所が挙げられます。
- 床の隅やカーテンレールに残った髪の毛やホコリ
- 蛇口や鏡に残る水滴や水垢
- ドアスコープやルームナンバープレートのくもりや汚れ
- アメニティやタオルの数が不足している
- ゴミ箱の袋がセットされていない
このような細かな部分まで意識してチェックするためにも、チェック項目が整理されたマニュアルが役立ちます。
日々の清掃作業を整理した清掃マニュアルと、仕上がり確認のためのインスペクションマニュアルという2つのマニュアルを併用することで、作業とチェックの視点をそろえやすくなります。
インスペクションマニュアルがあれば、チェック基準のバラつきをなくせる
現場でよくある課題のひとつが、どこまで確認すればOKなのかが人によって違ってしまうことです。
ベテランスタッフには当たり前のことでも、新人にはわからなかったり、解釈がずれていたりすることもあります。
しかし、インスペクションマニュアルがあれば、そうしたばらつきを防ぎ、誰が見ても同じ基準でチェックできる仕組みを作ることが可能です。
口頭で伝えるだけでは伝わりづらい細かなポイントも、マニュアルに整理しておくことで、共通認識としてチーム全体に浸透します。
なお、インスペクションマニュアルは清掃マニュアルとあわせて整理しておくと、日常清掃と点検の基準をすり合わせやすくなります。
「どの作業がどこまでできていれば合格か」「何をチェックすればよいか」が明確になり、品質の安定につながるでしょう。
マニュアルがあれば、OJTでは伝えきれない内容もカバーできる
新人スタッフへの指導は、OJT(現場教育)が中心になることが多いですが、OJTだけではどうしても伝え漏れが起きたり、説明する人によって内容が変わってしまったりすることがあります。
そこで役立つのが、インスペクションマニュアルです。細かなチェック方法や注意点をマニュアルにまとめておけば、OJTでは伝えきれないポイントもしっかりカバーできます。
「教わったけれど、やり方がわからなくなった」「説明が人によって違う」といった不安を減らし、スタッフ全員が迷わず動けるようになります。

宿泊業界に詳しいアドバイザーが、あなたに合う職場をいっしょにお探しします。
宿泊業界での職務経験はありますか?
ホテル客室インスペクションマニュアル例|チェック項目を部位別に紹介
 beeboys / stock.adobe.com
beeboys / stock.adobe.com
インスペクションマニュアルには、具体的に「どこを」「どのように」確認するのかを明記しておくことが大切です。
ここでは、ホテル客室のインスペクションでチェックしたいポイントを、部位ごとにご紹介します。
客室ドア・入口周辺
 AlexPhotoStock / stock.adobe.com
AlexPhotoStock / stock.adobe.com
お客様が客室に入る前から、ホテルへの印象はすでに始まっています。客室の入口まわりの清潔感や設備の整い具合も、サービスの一部として見られていることを意識しましょう。
- ドアノブやドア枠に汚れ・手垢がないか
- 開閉時にギーッという音など異音がしないか
- ドアチャイムが正常に鳴るか
- ドアスコープ(のぞき穴)にくもりや破損がないか
- ルームナンバープレートが外れていたり、汚れていたりしないか
お客様にとっては客室の第一印象になる大切なエリアです。細かな部分も見落とさず、気持ちよく迎え入れられる状態を目指しましょう。
クローゼット・収納まわり
 torsakarin / stock.adobe.com
torsakarin / stock.adobe.com
クローゼットや引き出しなどの収納まわりは、お客様が滞在中に頻繁に使う場所です。
汚れや破損のチェックはもちろん、忘れ物が残っていないかも大切な確認ポイントになります。
- 扉の開閉がスムーズで、異音がしないか
- ハンガーの数や種類が規定どおり揃っているか
- 忘れ物が残っていないか(ポケットの中や引き出しの奥まで)
- 内部の照明がある場合は、正常に点灯するか
- クローゼット内のホコリや汚れが拭き取られているか
お客様がクローゼットなどの扉を開けた瞬間に不快感を与えないよう、細かな部分まで丁寧に確認しましょう。
水回り(バスルーム・洗面・トイレ)
 Takashi-Images / stock.adobe.com
Takashi-Images / stock.adobe.com
水回りは、お客様からのクレームが発生しやすい場所です。
見た目がきれいでも、水滴の拭き残しやカビ、水垢など、細かな汚れは意外と目につきます。
角度を変えたり、しゃがんだりして確認することがポイントです。
- 洗面台・浴槽・トイレに髪の毛や水滴が残っていないか
- 鏡や蛇口に水垢や拭き跡がないか
- ドライヤーが正常に作動するか
- 歯ブラシ・タオルなどのアメニティ類が不足なく揃っているか
- 排水口、シャワーヘッドの裏などにカビやぬめりが発生していないか
仕上がりの美しさと衛生面、どちらも欠かせないポイントです。
客室全体(ベッド・備品・床・窓)
 moonrise / stock.adobe.com
moonrise / stock.adobe.com
清掃後のインスペクションでは、ベッドまわりを含む客室全体を広い視点で確認します。
お客様が快適に過ごせる状態になっているか、お客様目線でしっかりチェックしましょう。
- ベッドメイキングが整っているか(シーツのシワ、髪の毛残りなど)
- 照明やテレビ、エアコンなどの電化製品が正常に作動するか
- 家具や備品に破損・汚れがないか(リモコンやデスクまわりも含む)
- 床に髪の毛やホコリが残っていないか
- 窓ガラスがきれいに拭かれているか
- カーテンがスムーズに開閉できるか(フック外れ・破損の有無)
- ゴミ箱に新しいゴミ袋がセットされているか
仕上がりを確認する際は、お客様が部屋に入って最初に目にする視点で見渡すことが大切です。
ホテル&旅館業界の就職・転職についての記事
ホテル客室インスペクションマニュアルの作り方のコツ

インスペクションマニュアルは、ただチェック項目を並べるだけでは、うまく活用されないかもしれません。誰が見てもわかりやすく、現場で使いやすい形にすることが大切です。
ここでは、実際にマニュアルを作成する際に意識したいポイントや、作り方のコツを紹介します。
見やすく、使いやすい形式にする
マニュアルは「作ること」よりも「使われること」が大切です。
チェックリストや写真付きマニュアル、チェックボックス方式など、現場で確認しやすい形式を意識しましょう。
また、紙にするのか、タブレットで表示するのかなど、使用シーンに合ったレイアウトを選ぶこともポイントです。
どこで・誰が・いつ使うのかを想定して、できるだけストレスなく確認できる形を目指しましょう。
項目の分け、粒度をそろえる
インスペクションマニュアルは、誰が見ても同じ判断ができることが大前提です。
そのためには、チェック項目の粒度(どこまで細かく書くか)を揃えておくことが必要です。
エリア別(ドアまわり・水回りなど)や動作別(開閉する、拭く、補充するなど)で整理しておくと、迷わず使えるチェックリストになります。
マニュアル作成時に気をつけること
マニュアル作成の際は、現場で本当に役立つ内容になっているかを意識しましょう。
そのためにおすすめなのが、現場スタッフとすり合わせながら項目を作ることです。実際の作業を確認しながらチェック項目を考えることで、抜け漏れを防げます。
また、「確認する」「整える」などの曖昧な表現は避け、具体的なアクションで記載するのがポイントです。
たとえば、「ドライヤーを確認する」ではなく、「ドライヤーの電源が入り、風が出るか確認する」と書くと、誰が読んでも迷わず判断できます。
清掃マニュアルとインスペクションマニュアルの内容をすり合わせておくと、作業者とチェック担当者の間で認識のずれが生まれにくくなるでしょう。
外国籍スタッフにも伝わる工夫を入れる
2019年にスタートした「特定技能制度」により、宿泊業でも外国籍スタッフの採用が広がっています。
この制度は、一定の技能や日本語能力を持つ外国人が、日本で働くことを認める在留資格のひとつです。
外国籍スタッフといっても、英語が得意とは限らず、英語圏以外の出身だったり、専門用語が難しかったりするケースもあります。
そのため、伝えたつもりにならない以下のようなマニュアルづくりが大切です。
やさしい日本語やシンプル英語で表現する
外国籍スタッフにもマニュアルの内容をしっかり伝えるためには、使う言葉選びが大切です。
「ご確認ください」「整えてください」といった敬語や抽象的な表現は避け、短くシンプルな言葉で、具体的に書くことを意識しましょう。
たとえば、日本語の場合は「ゴミ箱の袋を交換してください」ではなく、「ゴミ箱に新しい袋を入れる」といった表現にするだけでわかりやすくなります。
英語の場合も同じく、簡単な単語と短い文章を使うと伝わりやすくなります。
- Check if the trash bin has a new bag.(ゴミ箱に新しい袋があるかチェックする)
- Make sure the towels are folded neatly.(タオルがきれいにたたまれているか確認する)
曖昧な言い回しを避けて具体的に書くことで、誰が読んでも同じ判断ができ、説明する人によって伝え方が変わってしまうことを防げます。
こうした表現は、日本人スタッフにとっても理解しやすく、教育の負担を減らすことにもつながることが期待できます。
視覚で伝える工夫を取り入れる

言葉だけで説明しようとすると、細かなニュアンスが伝わりにくかったり、理解に時間がかかったりすることがあります。
特に、清掃後の仕上がりや備品の配置などは、写真やイラスト、ピクトグラム(案内用の絵記号)を使って視覚的に伝えるのが効果的です。
たとえば、スリッパの向きやリモコンの置き場所など、感覚に頼りがちな部分は、「OK例」「NG例」を写真で並べると、誰でもすぐに判断できるようになります。
外国籍スタッフといっても、必ずしも英語が得意とは限りません。
英語圏以外の国から来ている場合や、英語は話せても専門用語まではわからないこともあります。
そのため、言葉だけに頼らず、視覚的に伝える工夫が役立ちます。
自動翻訳に頼りすぎない工夫をする
翻訳ツールはとても便利ですが、掃除や設備まわりの専門用語は正しく訳されないこともあります。
たとえば、「排水口」「拭き跡」「アメニティ」など、日常会話ではあまり使わない言葉は、誤訳されるケースが少なくありません。
そのまま翻訳に頼りすぎると、かえって誤解を生んでしまうおそれもあります。
翻訳結果はそのまま使うのではなく、実際にスタッフと確認しながら、必要に応じて簡単な言葉に置き換えたり補足を加えたりすることが大切です。
「この言い方で伝わるか?」を現場で試しながら調整することで、より伝わるマニュアルづくりにつながります。
英語(外国語)チェックリストを用意する
外国籍スタッフにも迷わず作業してもらうためには、日本語だけでなく、英語や必要に応じた外国語でチェックリストを用意しておくことが効果的です。
「Check」「OK」「NG」など、シンプルな表現を使い、短い文でわかりやすくまとめると、英語が得意でないスタッフにも伝わりやすくなります。
たとえば、英語のチェックリスト例は以下のような形です。
| 英語項目名 | 英語チェック内容 | 日本語訳 |
| Trash bin | New bag inside? | ゴミ箱 → 新しい袋が入っているか? |
| Towels | Folded neatly? | タオル → きれいにたたまれているか? |
| Door | Opens and closes smoothly? | ドア → スムーズに開閉するか? |
必要に応じて、写真やイラスト、ピクトグラムとセットにしておくと、さらに伝わりやすくなるでしょう。
スタッフの母国語を考慮した多言語対応も取り入れると、より安心して作業できる環境づくりにつながります。
作って終わりにしない!インスペクションマニュアルを活用・改善するコツ

インスペクションマニュアルは、作っただけで満足してしまうと、すぐに使われなくなったり、内容が現場の実態と合わなくなったりしてしまいます。
せっかく作ったマニュアルを、現場でしっかり活用し続けるためには、運用方法や改善の工夫が欠かせません。ここでは、マニュアルを作って終わりにしないためのポイントを紹介します。
使われるマニュアルにする工夫を取り入れる
せっかく作ったマニュアルも、使われなければ意味がありません。現場で実際に使ってもらうためには、すぐ確認できること、わかりやすいことが大切です。
具体的には、次のような工夫を取り入れると効果的です。
- チェックリスト形式にする
- チェックボックスや写真を活用する
- 紙・タブレットなど、使用シーンに合った形で用意する
スタッフが「確認するのが面倒」と感じると、チェックが形だけになってしまいがちです。
簡単に使える工夫を取り入れて、自然と確認する習慣が身につくマニュアルを目指しましょう。
スタッフの声を集めて改善につなげる
マニュアルをよりよくするためには、現場で実際に使うスタッフの声を取り入れることが欠かせません。
「この項目がわかりにくい」「こうした方が確認しやすい」といった意見は、改善の大きなヒントになります。
たとえば、ミーティング・アンケートなどを活用し、定期的に意見を聞く場を設けるとよいでしょう。
そこでスタッフから出た意見は、できるところから反映していくことがポイントです。
現場のリアルな声を反映したマニュアルほど、スタッフにとって使いやすいツールになります。
定期的に見直して更新する
業務の流れや設備は、時間とともに変わることがあります。そのため、マニュアルは作りっぱなしにせず、定期的に内容を見直すことが大切です。
どのタイミングで、どんな点を確認すればよいか、あらかじめ決めておくと安心です。たとえば、次のようなタイミングで見直しを行いましょう。
- 半年ごと、年に1回など、定期的なタイミングを決める
- 繁忙期が終わったあとや、新人が入ったときにチェックする
- クレームやトラブルが発生したときは、該当箇所をすぐに確認・更新する
更新を定期的にすることで、現場に合ったマニュアルをいつでも使いやすい形で保てるようになります。
OJTや勉強会で活用する
マニュアルは日々の点検だけでなく、新人教育やスタッフのレベルアップにも役立つツールです。
OJTや勉強会の中でマニュアルを使えば、指導する内容のばらつきを防ぎ、「何をどう見ればいいのか」が誰にでもわかる状態をつくれます。
具体的には、次のような場面でマニュアルを活用すると効果的です。
- 新人研修でマニュアルを見ながら説明する
- 実際にOK例・NG例を見せながら、判断基準をそろえる
- 定期的な振り返りの場でもマニュアルを確認する
活用する場面を増やすことで、マニュアルは見るだけのものではなく、学びのツールとしても根づいていくでしょう。
出典:在留資格「特定技能」とは/公益財団法人 国際人材協力機構インスペクションマニュアルで、ホテル客室の品質を守り続けよう
インスペクションマニュアルは、客室清掃の品質を安定させ、スタッフ全員が同じ基準でチェックできる仕組みをつくるための大切なツールです。
一度作ったら終わりではなく、現場の変化に合わせて改善しながら活用することで、より使いやすく、役立つマニュアルになっていきます。
清掃ミスを防ぎ、安心してお客様をお迎えできる客室づくりのために、ぜひマニュアルづくりや見直しに取り組んでみてください。
もし、インスペクション業務をはじめとしたホテルのお仕事に興味がある方は、おもてなしHRもぜひご利用ください。
宿泊業界専門の就職・転職支援サービスとして、あなたに合ったお仕事探しのサポートをいたします。
おもてなしHRに相談する


















 Facebookでシェア
Facebookでシェア X(Twitter)で投稿
X(Twitter)で投稿