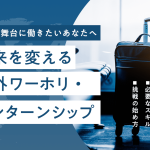アクセシブルツーリズムとは

ifotolia- stock.adobe.com
「アクセシブル」は直訳すると「近寄りやすい・使いやすい」という意味です。近年では「心身の機能に何らかの制限がある人も無い人も使いやすいこと」を指して使われる機会が増えました。
障がいのある人専用の特別なものを用意するのではなく、どんな人でも快適に使えることを重視する考えで「ユニバーサルデザイン」と同義で使われる言葉です。身近なものでは、シャンプーとリンスを区別するためのボトルの刻みや、電卓やテンキーの「5」に付いている突起などが挙げられます。
このような工夫で、障がいのある人にも無い人にも快適な旅を提供するのが「アクセシブルツーリズム」なのです。
なぜアクセシブルツーリズムが必要なのか

motortion- stock.adobe.com
なぜアクセシブルツーリズムが必要なのかを考えていましょう。今、日本は少子高齢化で消費者人口が減少しています。そこで障がいや、高齢などが理由でレジャーを諦めかけている層の、多種多様なニーズに応えて新たな顧客を獲得する必要があるのです。
また、全ての人に自由で快適な旅を提供することは、社会的にもとても意義のあることです。アクセシブルツーリズムは、企業の利益を追求するだけでなく、誰もが旅の楽しみを持って明るい気持ちで生活できる社会づくりにも貢献できる取り組みです。
アクセシブルツーリズムへの取り組み

ggfoto- stock.adobe.com
近年、アクセシブルツーリズムへの取り組みが盛んに行われています。障がいの有無に関わらず、快適で楽しい旅行を提供するためにどのような取り組みがされているのでしょうか。事例を交えて紹介します。
誰もが使いやすい設備やサービス
アクセシブルツーリズムを推進する観光地では、設備をアクセシブルデザインにしています。極力段差を無くしてフラットな空間を作り、階段だけでなく緩やかなスロープを設置している施設では、足に不自由がない人でもつまづきや転倒の恐れが少なく安心ですね。
車いすや松葉杖の人が無理なく通れる広く設計した出入口や、読みやすい大きな文字で掛かれた案内看板も、みんなにとって使いやすいものです。また、オストメイト対応の広いトイレや、音声ガイドの機能が付いた観光案内版なども各地で導入されています。
そして、設備だけでなく障がいのある方に適切な対応ができるスタッフの配置も推進されています。浅草で人力車のサービスを提供する企業では、手話ができる車夫が在籍しており、耳の不自由な方に手話での案内を提供しています。
他にも多数の観光業の企業で、車いすの方や、視覚・聴覚に障害のある方のお手伝いをするための研修が行われています。
アクセシブルツーリズムのポータルサイトやガイドブック
心身の機能に制限のある人が旅行を躊躇する原因のひとつに「自分の障がいに対応してくれる施設を探すのが大変」ということがあります。
旅先では、交通機関に宿泊先、レジャースポットやお土産やさんなど様々な施設やサービスを利用しなければなりません。それらをひとつずつアクセシブルツーリズムに対応しているかどうか確認するのは確かに骨の折れることでしょう。
こうした手間を極力省くために、アクセシブルツーリズムに対応している観光施設の情報をまとめたポータルサイトや、ガイドブックがあります。
東京都では特に力を入れており、アクセシブルツーリズムに対応した30の観光コースをポータルサイトで提案しています。エスカレーターやオストメイトトイレの位置もマップで確認できるので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
シンポジウムやワークショップの開催
アクセシブルツーリズムの認知度を上げ、さらに推進するために全国各地でシンポジウムやワークショップが開催されています。
令和2年の1月に東京都で行われたシンポジウムでは、事故である日突然然両下肢マヒになった、車いすのアイドルによる講演や、元パラリンピック選手や宿泊業・観光業の関係者によるパネルディスカッションが行われました。
また、アクセシブルツーリズムは海外でも盛んに取り組まれています。2018年の12月にはインドネシアにて、日本の国際機関とASEAN諸国の観光関係省庁の代表者が参加するワークショップが開かれています。
このワークショップでは、障がいのある人にとって困難だったビーチリゾートでの観光についての講演がメインに行われ、日本の先進的なアクセシブルツーリズムの事例がSEAN諸国に共有されました。
アクセシブルツーリズムは、企業の利益を出すためだけの取り組みではなく、社会福祉の一環でもあります。知識やアイディアを独占せずに、良い取り組みはどんどん共有して広めていくことが望ましいですね。
参照:東京都のアクセシブルツーリズムへの取り組みについて/東京都産業労働局
宿泊施設のアクセシブルルーム

poko42- stock.adobe.com
宿泊施設は当然のことながら、旅行に欠かすことができない重要要素です。アクセシブルツーリズムが推進される今、各宿泊施設でもアクセシブル化が進んでいます。中には「アクセシブルルーム」と呼ばれる客室を持つ施設もあります。アクセシブルルームは一般的な客室とどのような違いがあるのか見ていきましょう。
段差の無いフラットな構造
アクセシブル化が推進される観光施設や公共施設と同様に、アクセシブルルームは段差の無いフラットな構造になっています。一般的な客室では、入り口やトイレ、バスルームには段差があることが多いですよね。
アクセシブルルームではそういった段差を無くし、車いすでスムーズに移動できるように工夫されています。また、一般的な客室よりも低いベッドを採用し、テレビや絵画などが低いところに配置されることが多いです。
使いやすい水回り
アクセシブルルームでは、水回りも使いやすく工夫されています。特に重要なのは、転倒など事故が起きやすいバスルームです。バスタブや洗い場に手すりをつけたり、一般客室よりも強力な滑り止めを採用する施設が多くあります。シャワーチェアやバスボードの貸し出しを行うホテルもあります。
また、洗面台を工夫しているホテルもあります。水道蛇口が付いている下の部分が空いている机のような構造で、車いすの人にも使いやすく設計されています。
アクセシブルツーリズムの課題

polkadot – stock.adobe.com
旅行者の誰もが不自由しないことを目的としたアクセシブルツーリズムですが、この取り組みが広く認知されるようになったのは、比較的最近のことです。そのため、改善が必要な課題も少なくありません。具体的にどのような課題があるのか、考えていきましょう。
アクセシブルルームが少ない
前項目で紹介したアクセシブルルームには、客室数が少ないという課題があります。そのため人気の高いリゾートホテルなどでは常にアクセシブルルームは予約が埋まっており、宿泊したくてもできない人が多い状況だそうです。
心身の機能に制限の無い人は、アクセシブルルームでも一般的な客室でも問題なく滞在できますが、その反対ではそうは行かないですよね。各宿泊施設で、アクセシブルルームをさらに増やす努力が必要とされています。
アクセシブルルームが病室のようになりがち
アクセシブルルームの設備を充実させすぎて客室がまるで病室のような雰囲気になってしまうとう問題もあります。壁の至るところに取り付けられた無機質や手すりや、車いすでの通行に重きを置きすぎてガランと広いだけの印象の客室では、旅行に来たのだという高揚感が味わいにくいですよね。
車いすで全国を旅するある女性は、「障がいのある人や高齢者は、こんな設備が必要だろう」という想像で設計するとこのような部屋になりがちだ指摘しています。
お客様は非日常を楽しむために旅行に来ているということを忘れず、雰囲気を大切にしたアクセシブルルームづくりが必要でしょう。
アクセシブル化にはコストがかかる
既存の施設をアクセシブル化するにしても、新たにアクセシブル対応の設備を作るにしても、コストが掛かります。アクセシブル化は社会福祉の一環でもあるので、公的機関での費用の補助があることが望ましいですね。
観光庁では、2019年に宿泊施設のバリアフリー化を促進する事業が行われ、補助金を支給するための公募を行いました。客室や共有部分のバリアフリー化の事業計画を提出し、効果が特に高いと認定された施設に支給されるものでした。
また、東京都にもアクセシブル化に掛かる費用を補助する制度があります。アクセシブルツーリズムへの対応を検討するのであれば、利用できる公的な補助金があるかどうか調べてみましょう。
障がいの無い方への配慮を忘れがち
アクセシブル化を考える際には、障がいのある方の目線に立つことが重要ですよね。しかし、その一方で忘れがちなのは障がいの無い方への配慮です。
障がいのある方への負担を減らすことを考えるあまり、障がいが無い人へのおもてなしが手薄になったり、待ち時間が伸びたりするようなことがあれば、お客様同士の間に不公平感が生まれてしまいます。
アクセシブルツーリズムは本来、障がいのある人を特別扱いするのではなく、誰もが快適に楽しめる旅を提供することが目的です。もちろん障がいのある方にはそれぞれに適し配慮や手助けが必要です。しかし、それと同じくらい障がいの無い人への配慮も大切にしなければ、本当のアクセシブルツーリズムとは言えないのです。
参照:東京都のアクセシブル化費用補助について/東京都産業労働局
アクセシブルツーリズムはどの人にも快適な旅

taka- stock.adobe.com
アクセシブル化された観光施設や宿泊施設、公共交通機関はだれにとっても使いやすいものです。アクセシブルツーリズムがより広く浸透し、一般的なものとなれば障がいのある人も無い人も、より快適で便利な旅が楽しめるようになるはずです。補助金の制度もありますのでぜひ、施設のアクセシブル化を検討してみましょう。






 Facebookでシェア
Facebookでシェア X(Twitter)で投稿
X(Twitter)で投稿