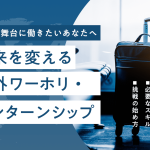なぜ政府がインバウンド誘致に乗り出したのか

Free1970- stock.adobe.com
「インバウンド」とは「外から内へ」という意味のある言葉です。日本においては、観光旅行などで海外からやってくる人のことを指します。今、日本の政府はインバウンド客の消費を拡大するべく、さまざまな政策に乗り出しています。
この背景には、少子高齢化により日本国内での消費が減少しているとうことがあります。日本の魅力を海外に広くアピールし、減少した国内消費をインバウンド客の消費でカバーしようという算段なのです。

宿泊業界に詳しいアドバイザーが、あなたに合う職場をいっしょにお探しします。
宿泊業界での職務経験はありますか?
観光庁によるインバウンド政策

sakura- stock.adobe.com
インバウンド政策は、観光庁による取り組みです。東京オリンピックが開催される2020年に4000万人のインバウンド客を呼び込むことを目標に掲げ、2012年から活動が始まりました。開始以来、着実にインバウンド客を増やしています。具体的な活動内容を見ていきましょう。
訪日プロモーション活動
インバウンド客誘致は、まずは海外の人に日本に興味を持ってもらうことから始まります。観光庁では各国のニーズや国民性を考慮し、その地域に合ったプロモーション活動に取り組んでいます。
歴史やアクティビティに関心の高い欧米豪市場には、山伏修行体験やスキューバダイビングなどを、個人の趣味趣向を特に重要視するアジア市場には、食べ歩きやポップカルチャーに触れる旅をアピールしています。
さらに細かく、タイに向けては「特定テーマ深掘り」イタリアに向けては「旅行先としての日本認知度向上」など、国ごとに方向性を定めて取り組まれているのです。
ウェブの閲覧・検索履歴を分析するオンライン広告を活用し、個人が持っている興味・関心をピンポイントで狙ったプロモーション活動も行われています。
MICE(マイス)誘致
MICE(マイス)とは、海外企業の研修や国際会議などを指す言葉です。観光客だけでなく、MICEの誘致もインバウンド政策による取り組みの一部です。
この取り組みは、インバウンドの人数を増やし、地域に経済効果をもたらすという直接的な効果の他、日本国内の関係者と海外の関係者とのネットワークを作ることや、新しいビジネスなどの機会を生み出す効果も狙っています。誘致のため、下記のような活動が行われています。
- グローバルMICE都市として12都市を選定し、地域関係者の連携を強化するなどの支援
- 歴史的建造物などの「ユニークアベニュー」を会場として利用可能にすることを促進
- 産業界や学術分野で国内外に発信力やネットワークのある人をMICEアンバサダーに任命
こうした取り組みによって、2018年に日本で開催された国際会議は429件に上りました。
これは世界で7番目に多い件数です。
自治体向けの安心・安全相談窓口の設置
実際にインバウンド客の対応に当たるのは現地の人です。観光庁では、インバウンド客を受け入れる自治体をポートするための、安心・安全相談窓口を設置しています。この窓口はインバウンド客の数に比例し、ケガ・病気などのトラブルが増加したことで設置されました。
トラブル発生時に電話で相談すれば、事例に沿ってのアドバイスを貰えたり、関係府省庁などへの橋渡しなどのフォローを受けることができます。
参照:プロモーション活動について/訪日旅行促進事業(訪日プロモーション)
ホテル&旅館業界の就職・転職についての記事
官民が協力し合う「ビジット・ジャパンキャンペーン」

vinnstock- stock.adobe.com
国土交通省を中心に、官民が協力し合う「ビジット・ジャパンキャンペーン」という取り組みもあります。ビジット・ジャパンキャンペーンは、2003年に「2010年に訪日外国人を1,000万人」を目標に掲げて発足しました。下記5つの事業を中心に、世界に日本をアピールしています。
- 現地消費者向け事業
- 現地旅行会社向け事業
- 在外公館との連携事業
- 官民連携事業
- 地方連携事業
具体的な活動としては、訪日促進重点国を選定し、それぞれに合わせたPR活動を行う、観光ビザを緩和する、芸能人などを親善大使に任命してアピールするといった取り組みがされています。
その結果、発足当時年間で521万人だったインバウンド客数が、2013年に目標の1000万人に達しました。2010年前後の年は、リーマン・ショックや東日本大震災などでインバウンド客が落ち込む時期があったため目標から3年遅れでの達成です。
インバウンド政策による成果

beeboys- stock.adobe.com
インバウンド政策が本格的に始まり、インバウンド客の数も、インバウンド客が日本で消費する金額も年々増え続けています。具体的な推移を見ていきましょう。
訪日人数の推移
観光庁のインバウンド政策が始まった2012年から、2018年までの訪日人数の推移は以下の通りです。
- 2018年/31,191,856人
- 2017年/28,691,073人
- 2016年/24039700人
- 2015年/19,737,409人
- 2014年/13,413,467人
- 2013年/10,363,904人
- 2012年/8,358,105人
毎年、着実に伸びています。ここまで伸びた背景には、先述の地域ごとのPR活動やMICE誘致の他、円安の影響やLCC(格安航空会社)の日本就航などもあります。
2017年から2018年の間は他の期間に比べて伸び率が低いですが、中国以外の東アジアで、台風の被害が甚大だったことが影響しています。
インバウンド客ひとりあたりの消費金額の推移
インバウンド客の国内消費額の推移も見てみましょう。インバウンド客数と同様に、2012年から2018年の期間です。
- 2017年/153,921円
- 2016年/155,896円
- 2015年/176,167円
- 2014年/151,747円
- 2013年/136,693円
- 2012年/129,763円
2015年に大きく伸びています。この年は中国からのインバウンド客による「爆買い」が流行しました。背景には中国の元高や、税制により一部の日本製品が中国内で購入するよりも、日本に購入して持ち帰った方が大幅に安く購入できたことがあります。
また、日本の免税品の拡大も影響しました。それ以降は1人当たりの消費金額に大きな変動はありませんが、インバウンド客数が増えているためトータルでのインバウンド消費金額は大幅にアップしています。2012年が2012年が836億円だったところ、2018年には4兆5064円にまで上りました。
参照:インバウンド客数・消費額の推移について/日本政府観光局資料・観光庁資料
インバウンド政策の今後の展望は

siro46- stock.adobe.com
これまでも大きな成果を出してきたインバウンド政策ですが、少子高齢化の日本経済を回していくには今後も取り組みを続ける必要があります。インバウンド政策の今後の展望を見てみましょう。
オーバーツーリズムの解消に取り組む
インバウンド客の増加により、日本全国で「オーバーツーリズム」が発生しつつあります。オーバーツーリズムとは、土地にキャパシティ以上の人数が旅行に来ることで起こる問題のことを指します。
- 交通渋滞
- 騒音
- トイレの不足
- ゴミの問題
- 無断の写真撮影
上記のようなことがあげられます。また、これらが原因で起こる地域住民と旅行客とのトラブルもオーバーツーリズムです。観光立国を目指すには、オーバーツーリズムへの適切な対策が不可欠です。日本では2019年6月に、観光庁がオーバーツーリズム問題の調査に乗り出し、国内外の先進事例を参考に対策を講じることを発表しました。
大勢の観光客が押し寄せるスペインのバルセロナでは、オーバーツーリズムが原因の「反観光デモ」が起こっています。日本でも同じことが起こるのではと懸念する声が少なくありません。先手を打つことが重要です。
IR整備をサポート
2016年12月、日本でのカジノを解禁する「カジノ法案」が可決されました。カジノを含む統合型リゾート施設(IR)の建設地として、大阪や横浜などの都市が立候補しています。日本にIRがオープンすれば、インバウンド客数・消費額がますます増加し、日本経済が活性化する可能性が高まるでしょう。
一方、IR誘致を検討しているどの地域にも反対派が居ます。共通の懸念点は、ギャンブル依存症が増えることです。しかしながら、カジノ施設ができた後にギャンブル依存症患者が減少したという例もあります。
政府公認のカジノがあるシンガポールでは、ギャンブル依存症の治療施設を設立したのです。この政策が功を奏し、カジノ施設ができる前に比べてギャンブル依存症患者が大幅に減少しました。
また、日本のカジノ施設においては、日本人や在日外国人は週3回、月10回までの入場制限を設けることや、申し出れば自分や家族を出入り禁止にできるプログラムの導入が予定されています。
今後、シンガポールなどの成功事例を参考にさらなる対策が検討されていくことでしょう。
参照:オーバーツーリズム対策について/持続可能な観光先進国に向けて
海外の観光政策について

thaifairs- stock.adobe.com
海外でも観光政策に力を入れている国は多数あります。今回は、特に観光先進国と呼ばれる、アメリカとフランスにスポットを当てて取り組みを見てみましょう。
アメリカの観光政策
アメリカは連邦国家であるため、法律や条例が州ごとに異なりますよね。観光政策もそれと同様に、州や町がそれぞれに観光マーケティングを行うことが一般的でした。
このような背景から、アメリカには国レベルで観光に取り組む機関が長い間無かったのです。しかし、2010年に全州をあげて観光客を誘致する「Brand USA」が設立されました。
設立の目的は、観光地としてのアメリカの魅力を世界にもっと広め、訪れる人を増やすことです。アメリカを訪れる際の手順やポリシーを世界の人に正しく伝えるため、多言語化を促進するなどの取り組みも行われています。
フランスの観光政策
フランスは世界一の観光大国です。歴史的建造物や美術品、自然の風景など観光資源に恵まれていることも理由ですが、ユニークな行政のサポートも大きく影響しています。
フランスの行政は2020年に一億人の観光客誘致を目標に掲げています。そのための取り組みとして、各地域に毎年約3000万円ほどの予算を配布し、各地域の効率を評価してランキングを発表するのです。
競争関係を作ることで互いに切磋琢磨し、より良い観光地となっていくのですね。あえて競争関係を作り出すという手法はさすがフランスです。
そんなフランスですが、地元の人が観光客に冷たくしがちという課題があるそうです。世界を股にかけるある旅行サイトの調査によると、観光客への不親切度ランキングの1位はフランスでした。
フランス現地の人々は、大量の観光客がやってくることにうんざりしているのかもしれません。これもオーバーツーリズムでしょう。このような意見を受けて、フランスの観光政策に精通した専門機関が主体となり、世界各国の観光客の特徴やどのような対応が喜ばれるかをまとめたマニュアルを配布したそうです。
成功に向かうインバウンド政策

kyo- stock.adobe.com
不景気が続く現在「日本の政策」という言葉には、マイナスイメージを持つ人が多いかもしれません。しかし、インバウンド政策については、やった分だけきれいに成果が現われていることがデータから分ります。
インバウンドは、政策に限らず民間企業や個人事業でもこれからのチャンスが大きい分野です。今回紹介したインバウンド政策を参考に、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。



















 Facebookでシェア
Facebookでシェア X(Twitter)で投稿
X(Twitter)で投稿