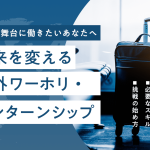不足から一転、ホテルは供給過剰の状態

show-m – stock.adobe.com
東京オリンピックにIR誘致、国際的なスポーツイベントや会議など、日本では今、さまざまな手法でインバウンド客や国内旅行者を呼び込み、観光立国となることが目指されています。
こうした動きの中、数年前まではホテルのキャパシティ不足が叫ばれていましたよね。しかし、その状況は一転し、2018年ごろから反対にホテルは供給過剰だと言われるようになりました。
供給過剰となった理由はどのようなことでしょうか。また、それによってもたらされた影響や、この先の生き残りに必要なことを考えて行きましょう。
なぜホテルは供給過剰になったのか?

lapisu- stock.adobe.com
ほんの数年前まで「足りない!足りない!」と言われていたホテルの客室数ですが、なぜ供給が過剰になったのでしょうか。その背景には、インバウンド政策や消費のトレンド、国際的なイベントへの備えなどが関係しています。
東京オリンピックへの備え
ホテル不足を懸念する声が高まったのは、2020年の東京オリンピックが決定した2013年からのことです。これを受けて、東京・大阪などの都市部を中心に全国各地でホテルの建設ラッシュが続き、2018年に客室数が大幅に増えたことでホテル不足は解消されました。
東京オリンピックの動きを推測する複数のシナリオで「ホテル不足は発生しない」と発表されたこともあり、不足の懸念に取って代わり「ホテルは供給過剰では?」という声が出てきたのです。
インバウンド需要による増加
高まるインバウンド需要に対応するために、ホテルを増やしたことも供給過剰になった大きな要因のひとつです。インバウンド政策や円安の影響で海外からの旅行者が急激に増え、人気観光地ではホテルを増やしても客室が足りず、宿泊料金も非常に高騰するという事態でした。
特にインバウンド客からの人気が高い大阪では、ホテルが足りずに兵庫や京都にお客様が流れてしまう状況であったため、続々とホテルの新規オープンが進み、ホテル建設のバブルとなりました。
また、規模の大小はあれど全国の観光地でも似たような事象が発生し、日本のどこかしらで常に新しいホテルがオープンしている状況が数年間続いたのです。
旅館業法の規制緩和で新規参入の増加
旅館業法の規制緩和も、ホテルなどの宿泊施設が増えた要因にあげられます。最低客室数の廃止や、玄関帳場の規制の緩和などにより、旅館業法の営業許可を取得することのハードルが非常に低くなりました。
そのため、使っていない土地を持っている人や、別事業を営む企業がホテル業界へ参入したり、簡易宿泊所に着目していた企業がホテルの開業へ乗り出すといったことが起こりました。
コト消費の流行
今の消費のトレンドは「コト消費」です。モノを購入するよりも、独自の体験をすることにお金を使いたいと考える人が増えています。この傾向は、宿泊業界にも大きな影響を与え、個性的なホテルが続々と誕生していきました。
個性的なホテルは人が集まる都市部に集中してオープンします。そのため、オリンピックやインバウンドの需要によってホテルを大増設した東京や大阪で、さらに母数が増えることになり、供給過剰に拍車が掛かることになったのです。
ホテルの供給過剰が与えた影響

milatas – stock.adobe.com
ホテルの供給過剰は、どのような部分にどういった影響を与えたのでしょうか。ひとつずつ確認していきましょう。
一軒あたりの宿泊客数が減少する
2020年3月現在、宿泊業界はコロナウイルスの影響で大打撃を受けています。しかし、コロナウイルスの流行により客足が遠のく以前から、一軒当たりの宿泊客数は減少傾向にありました。
旅行者数そのものは減少していない時期でも、ホテルの数が増えすぎたことで宿泊客が分散されたのですね。特に、ホテルの建設バブルが起きた大阪を中心とする関西地方では影響が顕著に現われ、供給過剰が浮き彫りになっています。
価格競争の勃発
ホテルの供給が需要を上回ると、宿泊代金の価格競争が始まります。コロナウイルスの流行で旅行客が激減している2020年3月現在でも、クーポンを出して顧客の呼び込みを図っているホテルが多い状況です。
コロナウイルス終息後も、閑散期を中心に価格戦争が勃発することが予想され、資金力の無いホテルは存続が難しくなったり、自転車操業に陥るかもしれません。
ホテルで働く人・働きたい人への影響
ホテル業界で働いている人・将来働きたいと考えている人にも、供給過剰は影響があります。ホテルの件数が増えると、それだけ働く人の数も必要になりますよね。ホテル業界はもともと人手が不足している業界でしたが、さらに不足しています。
2018年の大阪府では、ホテルの客室係の有効求人倍率が7倍に上ったほどで、外国人の採用も積極的に行っていますが、それでも足りない状況です。
ホテル業界へ就職したいと考えている人にとっては、採用されやすい良い時期と言えるでしょう。しかし、問題は入社後です。必要最低限の人員も確保できず、1人あたりの業務負担が大ききくなることや、ひょっとするとリストラ・倒産という事態になることも考えられます。
しかしながら、この不利な状況の中でもしっかりとした経営戦略のもと、安定した経営を続けているホテルもあります。ある大手ビジネスホテルチェーンの社長は業界全体が不利な今こそ、自社ホテルを伸ばすチャンスだと語っています。
現在、ホテル業界は楽観視できる状況ではないかもしれません。先見の明を持ち、ピンチをチャンスと捉える人材が、今後のホテル業界を牽引するのではないでしょうか。
供給過剰の状態でホテルが生き残るには?

beeboys- stock.adobe.com
供給過剰の状態で、今後もホテルを存続させるには、他社と差別化し、時代に合わせて変化し続けることが必要です。
例えば観光客向けのホテルが飽和状態ならば、ノマドワーカー向けのホテルを作る。ビジネスホテルが乱立しているのであれば、アッパークラス向けのホテルを作る。
このように特色を持たせ、お客様にあえて選んで貰えるホテルにするのです。単純な価格競争だけでは生き残りは難しい現代のホテル業界では、消費者のニーズを的確にとらえ、柔軟な経営をすることが鍵となります。
ホテルをブラッシュアップして供給過剰を乗り切ろう

123dartist- stock.adobe.com
これまで順調な経営を続けてきたホテルであっても、供給過剰の影響を受ける可能性は大いにあります。コロナウイルスがこの先どうなるのか、東京オリンピック終了後がどんな状況になるのかは、まだ誰にも分からないことですね。
先が見えない厳しい状況の中ですが、サービスや設備をブラッシュアップし、早い段階から他社との差別化を図りましょう。






 Facebookでシェア
Facebookでシェア X(Twitter)で投稿
X(Twitter)で投稿