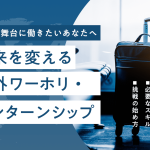観光標識とは?

iStock.com/recep-bg
観光地や主要駅などで、周辺の施設情報が乗った地図や、観光施設への道順を指し示した標識を見たことはありますか?こういった標識は「観光標識」と呼ばれており、国土交通省が定める作成のガイドラインがあります。
次の項目から、ガイドラインについて詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてくださいね。
観光標識のガイドラインはなぜ必要?

iStock.com/mattjeacock
観光標識の役割は、初めてその場所を訪れた人が道に迷わず目的地へたどり着くことを目的に作られています。観光標識があったおかげで迷子にならずに助かった経験を持つ人も多いのではないでしょうか。
非常に頼もしい存在の観光標識ですが、かつての観光地では、統一感の無い標識が乱立し、必要な情報が見つけくい常態でした。ごちゃごちゃと文字や絵が並んでいる上に情報がアップデートされておらず、何年も前に閉鎖した施設の情報がそのまま残っているということも珍しく無かったのです。
観光標識を見れば見るほど混乱するという、本末転倒な状況でしたが2005年に国土交通省が、分かりやすい観光標識を作成するためのガイドラインを設けました。
ビジットジャパンキャンペーンの発足に伴い、外国人観光客がひとり歩きできる観光地づくりをするための一環として、観光標識を一貫性のある、分かりやすいものに変えていく必要があったのです。
各観光地で定められたガイドラインに沿って観光標識を作成・設置することで、誰が見てもすぐに必要な情報が見つかるようになりますね。外国人観光客のみならず、地元の人の日常生活にもメリットがあることです。
観光標識のガイドラインの主な内容

iStock.com/XLXXL
観光標識のガイドラインは「観光客の視点に立って、誰もが見やすく分かりやすく行うべきである」という基本方針のもとに定められています。情報を常に新しいものにする、分かりやすい色を使うなど、細かな決まりごとが多数あります。具体的にどのような決まりがあるのか、ガイドラインの中から3つご紹介します。
ピクトグラムの活用
ピクトグラムとは、情報や注意を表わすためのシンプルな絵文字のことです。身近なものでは、お手洗いの男女マークや、禁煙を示すマークですね。
ピクトグラムは、観光標識でも積極的な活用が促されていますが、肝心なのは「何を表しているのかみんなに伝わる」ことです。そのため、ガイドラインでは「標準案内用図記号」に選定された、シンプルで分かりやすいピクトグラムを使用すると定められています。
「標準案内用図記号」の中に無い施設などをピクトグラムにしたい場合は観光標識の製作者で自作するとされています。ピクトグラムを考案するときは、分かりやすさを第一にしたいですね。
文字の表記の統一
観光標識のガイドラインでは、文字の表記も統一されています。表記が統一されてていると全体的にすっきりとまとまり、多くの情報の中から欲しい情報を探すことも容易になりますね。統一されている表記の一部を紹介します。
-
-
- 日本語と英語の併記もしくはピクトグラム、場合によっては多言語や音声での案内も付ける
-
-
-
- 固有名詞はローマ字、普通名詞は英語訳にする 例:「山下公園」→「Yamashita park」
-
-
-
-
-
- 日本語のローマ字表記はヘボン式にする
-
-
-
-
- 略語が慣用化されている場合は略語の表記も可能 例:「Station」→「Sta.」など
-
誘導形態に応じた配置
観光客の導線形態に応じた「自由アクセス型」「ルート設定型」や、一定のエリア・単一の施設へ観光客を誘導する「直接アクセス型」といった配置方法がガイドラインで推奨されています。また、通行の妨げにならない場所かどうか、車いすの人からも見えやすいかどうかなどを考慮する必要があります。
ガイドラインの基準未満だった観光標識の事例

iStock.com/izuseki
2013年、関西地方の観光地にて、設置されている観光標識がガイドラインの基準を満たしているかどうかの調査が行われました。ガイドラインの作成からしばらく経過したタイミングで行われた調査でしたが、残念ながら基準を満たしていない標識が多く見つかっています。
どのような部分が基準に達していなかったのか確認しましょう。
観光案内所の場所が古いまま
ある駅の南側に設置された観光標識では、観光案内所の位置が誤った場所に表記されているという点が指摘されました。
観光案内所が移転したにも関わらず、移転前の標識のままにしていたのです。観光案内所という重要設備の位置情報をいつまでもアップデートしないでいるのは考え物ですね。ガイドライン以前の問題です。
シンプルすぎる誘導サイン
温泉地の駅周辺に設置されていた、観光案内所への誘導サインは、方向を示す矢印と、日本語で「観光案内所方面」と書かれただけの非常にシンプルなものでした。英語表記もピクトグラムも無く、これでは日本語が読める人にしか分からないサインですね。
また、観光案内所にお手洗いや喫煙所などの設備があるのかどうかも分かりません。
分かりにくいお手洗い
温泉地にある公園内のお手洗いの標識は、ピクトグラムも英語の表記も無く、毛筆体で「お手洗」と書かれているだけのものでした。
おむつ変えシートやオストメイトトイレが備わっているかどうかも判断できないですね。日本人にとっても「入ってみないとどういうトイレか分からない」というのは不便でしょう。
観光標識のガイドラインを守るメリット

iStock.com/g_jee
ガイドラインはあくまでも指針であり、法律のように必ずしも守らなければならないものではありません。しかし、非常に合理的に考えて作成されているため、ガイドラインに従うことで、大きなメリットを得られる可能性があります。
観光標識のガイドラインを守って作成・設置をすることで、観光客が迷わず目的地にたどり着けます。迷子になって時間を無駄にすることが無いので、たっぷりと観光を楽しみ、お金をたくさん使ってくれることでしょう。観光地で働く人の道案内が楽になるメリットもあります。
また、標準案内用図記号のピクトグラムを使うことで、標識の素材を作る手間が省かれ、デザイン料などのコストの削減にもなります。オリジナリティのある観光マップも楽しいですが、大勢の人の目につく場所に設置する観光標識は、シンプルで分かりやすい物がやはりベストでしょう。
ガイドラインに沿った観光標識の設置で便利な観光地を作りましょう

iStock.com/Tatomm
2013年の時点ではいまひとつ浸透していなかった観光標識のガイドラインですが、観光立国を目指す日本では、どの国の人も不便なく観光できる街づくりが必要不可欠です。
観光標識や観光マップ、施設内の案内表示板を作成する際にはぜひ、ガイドラインを参照しましょう。
-






 Facebookでシェア
Facebookでシェア X(Twitter)で投稿
X(Twitter)で投稿