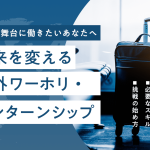農泊とは

iStock/okugawa
農泊とは、農⼭漁村において⽇本ならではの伝統的な⽣活体験と農村地域の⼈々との交流を楽しむ滞在(農⼭漁村滞在型旅⾏)
農林水産省「農泊の推進について」より引用
農泊は「グリーンツーリズム」と呼ばれることもあります。グリーンツーリズムはヨーロッパで始まった旅のスタイルで、「都会の喧騒を離れて農村や漁村でゆっくりと休暇をエンジョイする」ことを目的としています。
関連記事:グリーンツーリズムとは?メリットや事例も合わせて説明
日本は海外に比べて、農泊・グリーンツーリズムへの取り組みが遅れていました。しかし外国人観光客からのニーズの高まりや地方振興の観点から、最近では国も自治体も、農泊を積極的に推進する方向性を示しています。
なぜ農泊を推進するのか?

iStock/okugawa
なぜ国は、農泊を推進しているのでしょうか。農林水産省がまとめた「農泊の推進について」を見ると、以下のようなねらいがあることがわかります。
- ・農山漁村の所得向上をめざす
- ・インバウンドを含む観光客を呼び込み、活性化をはかる
- ・ビジネスとして整備する
昨今、東京などの大都市と地方の二極化が進んでいます。若い世代の人が地方から出ていってしまい、少子高齢化が進んでいるのです。
そうすると、空き家やシャッター商店街、事業の後継者不足などさまざまな問題が深刻化します。その地域からどんどん元気が失われていくのです。
農泊は、こうした状況を打開するための方法のひとつとして位置づけられています。
「コト消費」と農泊は親和性が高い

iStock/kumikomini
「モノ消費」「コト消費」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
数年前、「爆買い」が取り沙汰されたのは記憶に新しいです。これは外国人観光客が大挙して押し寄せて店のものを買いまくる、という現象で、モノ消費の代表例とも言えますね。
また「ゴールデンルート」と呼ばれる、外国人観光客に人気の観光ルートがあります。東京・富士山・京都・大阪といった定番のスポットを巡るもので、旅行会社が外国人観光客向けのツアーパックとして作っていることが多いです。
ゴールデンルートを巡りながら、買い物をしたり適度にアクティビティを楽しんだり。これが外国人観光客に人気の高い日本旅行でした。しかし近年では観光客の興味関心、ニーズが多様化してきており、もっと他の楽しみ方を求める声が増えています。
観光客向けにお膳立てされた遊びやモノを消費するのではなく、元から日本にあった生活を体験する、地元の人と交流する。こうした「コト消費」と呼ばれる旅行のスタイルに人気が集まっているのです。
そしてこの「コト消費」と農泊は非常に親和性が高いため、地方振興を助ける新たなインバウンド施策として期待されています。
農泊推進の具体的なアプローチ方法

iStock/HAKINMHAN
農泊を推進するための、具体的なアプローチ方法はどういったものでしょうか。
元々「農家に宿泊する」というスタイルは存在しましたが、これまでは住民の生きがい作りであったり、運営にかかる資金も公費に頼っていたりといった調子。到底ビジネスとはいえないものでした。
しかしこれを国や自治体がサポートし、ビジネスとして成立する仕組みを作ろうとしています。
国が掲げる具体的なアプローチ方法には、
- ・持続可能な産業
- ・自立的な運営
- ・法人格をもった推進組織をたて、責任の明確化を図る
- ・マーケティングに基づく多様なプログラム開発、販売、プロモーション、営業活動
などが挙げられます。農泊が軌道に乗れば、その地域に人が集まり、にぎわいが増し、経済的にもうるおう好サイクルを入手できるでしょう。
(農家)農泊と(農家)民宿との違いは?

iStock/DavorLovincic
農泊と農家民宿は字面が似ているため混同されがちですが、明確な違いがあります。それは、旅館業法の許可を得ているか否か、です。
民宿の運営には旅館業法の許可が必要ですが、農泊の場合は手続きの必要はありません。ただし自治体によって取り決めが異なるので、事前に確認は必要です。
旅館業法によると、旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、旅館業の許可を得ていない農泊は宿泊料を取ることができません。
しかし、体験プログラムの一環としてであればお金を取ることが可能です。そのため農泊には、その土地ならではの特色ある体験プログラムが多数用意されています。
農泊で提供するプログラムとは?
iStock/Rawpixel
農泊で提供するプログラムは多岐にわたります。
田植えや稲刈りなどの農業体験、里山ハイキングや魚のつかみ取りなどの自然体験、郷土料理教室などの料理体験などの他、林業体験、酪農体験、漁業体験などその土地ならではの個性あるプログラムも豊富です。
地方は都心部に比べて「見どころがない」「遊ぶところがない」と思われがち。しかし実はその土地に昔からあった資源・魅力を再発掘しブラッシュアップすることで、十分に観光客を惹きつける観光資源になり得ます。
自分たちの住む地域の魅力は何か、観光客に喜んでもらうために何ができるのか。住民が主体的にこれらのことを考え、実践することが地方に元気を取り戻すきっかけのひとつになるでしょう。
農泊でインバウンドを呼び、地方を元気に

iStock/Young777
「観光立国」を目指す日本は、さまざまなインバウンド向け施策を行っています。農泊は、その中のひとつとして位置づけられます。
例えば昔ながらの田園風景は、地元の人にとっては目新しさのない見慣れた風景ですが、海外からやってきた観光客にとっては新鮮で目を見張るものかもしれません。
昨今、「コト消費」が注目されているように、風景をただ見たりその土地の土産物を買うだけでなく、実際に体験することに重きが置かれています。田んぼや畑が広がる土地なら、田植え体験や稲刈り体験などをプログラムとして用意すれば、観光客に喜ばれるでしょう。
ただ日々を過ごすだけでは、こうした発想はなかなか生まれません。住民が地域の問題を自分ごととして考え、主体的に行動することで、地域の中から新たなにぎわいが生まれるはずです。
都心部と地方の二極化が問題視されて久しいですが、農泊事業はこうした地方のさまざまな問題を解決する一手として注目されています。






 Facebookでシェア
Facebookでシェア X(Twitter)で投稿
X(Twitter)で投稿