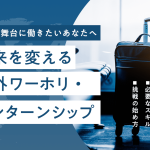ホテルが行うべき危機管理とは

iStock.com/undefined-undefined
火災や大規模震災など、万が一の事態が起こった際には、その場にいる人全員の身の安全の確保が最優先です。特にホテルは大勢のお客様や従業員が長時間を過ごす場所。ひとつ判断を誤るだけでも被害が拡大してしまいます。
また、想定できる危機も多様で、それぞれに適切な対処が必要です。
想定できる危機の種類とホテルで取るべき対策

iStock.com/etrovich9
火災
火災対策でもっとも重要なのは、未然に防ぐことです。
ホテルには、厨房や喫煙ルーム、キャンドルサービスなどで火を扱う場面が多数あります。従業員が火の扱いに気を付けることはもちろん、煙草の消し忘れが無いように、お客様へも張り紙などで注意を促しましょう。
火災報知機や消火器のメンテナンスも重要です。
万が一火災が起こってしまったらお客様を避難誘導し、従業員も安全なところに避難させてください。定期的に避難訓練を実施し、避難回路、避難計画を従業員全員が把握しておきましょう。
火元が小さければ消火器による初期消火で食い止められることもあるので、消火器の扱い方も学んでおくと良いですね。
地震
地震は、防ぐことも予想することもできない災害なので、被害を最小限に食い止めるための危機感が必要です。
大きな揺れの後には、避難経路の確保のためにドアや窓を開けましょう。そして二次災害を防ぐために火の元栓を閉めてください。ホテルの立地によっては地すべりや津波が起こる危険性もありますので、避難場所、集合場所を決めて従業員全員で共有しましょう。
また、建物そのものが倒壊すれば大惨事になります。耐震改修促進法の改正によって、旧耐震基準で建築された宿泊施設はすでに耐震診断や耐震改修をしていますが、定期的な点検や補修も必要です。
そして、宿泊客人数、従業員数に間に合うだけの非常食や水、簡易トイレやトイレットペーパーなどの物資も備えましょう。物資やスペースに余裕のあるホテルでは、帰宅困難者の受け入れを行うこともあります。
しっかりと備えておけばより多くの人の助けになり、事態が落ち着いたころに、泊まりに来てくれる方も居るでしょう。
風水害
台風や大雨による被害も想定されます。地震や火災に比べると軽い災害のように感じられるかもしれませんが、油断せずに安全確保に努めましょう。実際に2019年の台風19号では、全国で合計178軒の旅行やホテルに被害が出ました。
被害の内容は浸水や屋根の破損、露天風呂が全壊した、など深刻なものです。こういった被害最小限に抑えるには、まずは日ごろからの建物の点検が重要です。そしていざ台風が来た時は、飛来物から建物を守るためのネットを張る、建物周囲の植木や装飾物を室内に入れるなどの対策をします。
また、ニュースを随時確認し、交通情報や台風進路など、お客様への情報提供も行います。
感染症
ホテルはさまざまな人が集まる場所なので、感染症の危機管理も重要です。
出入口にアルコール消毒液を設置する、水回りや客室の除菌、空気清浄機の導入など防ぐための対策が取られています。
しかしながら、目に見えないウィルスなので完全にシャットアウトすることはほぼ不可能です。万が一発生してしまったら、拡大させないための措置を取ることが大切です。
発生を確認した場合は迅速に発症者を特定し、拡大を防ぐために隔離し、病院へ送ります。発症者と接触した従業員や近くに居たお客様もできるかぎりの消毒をして、病院で検査を受けましょう。対応が不適切だったために、合計で400人を超えるノロウイルスの感染者が出たホテルの事例もあります。
そのホテルでは、ノロウィルスに感染した宿泊客のひとりが廊下の絨毯に嘔吐しました。その吐しゃ物の処理の際、洗剤で掃除するだけで検査や消毒がされなかったために感染が拡大した可能性が高い、とされています。
従業員による不祥事
ここ数年の間で、飲食店や小売店の従業員が、SNSに業務に関わる不適切な投稿をして問題となる事例が増えています。ホテル業界でも、芸能人が宿泊しに来たことを投稿して炎上した事件がありましたね。SNSの問題の他にも、インサイダー取引や横領、ハラスメントなど従業員が問題を起こしホテルの評判が下がる危険性があります。
こういった従業員による不祥事が起こる企業は、経営理念が浸透していない、報連相ができていない、一般社員が上層部に意見できない、という社風である点が共通しているそうです。従業員個人の人間性というところでもあるのでしょうが、不祥事を起こさせない企業の風土づくりも、大切な危機管理です。
どの従業員にも発言の機会を与え尊重すると同時に、処罰を明文化し「どんな小さな不祥事でも許さない」という姿勢を見せることが対策になります。定期的なコンプライアンス研修を行うことも有効です。
危機管理の良い事例と悪い事例

iStock.com/bankrx
災害発生時に危機管理をきちんと行っていた事例と、行っていなかった事例を紹介します。
良い事例
東京都内のあるホテルでは、東日本大震災が発生した日の夜、約2000人の帰宅困難者を受け入れました。
宿泊客や従業現場従業員の員の安全を確保するだけでも大変な状況の中、ロビーや宴会場を開放し、お茶や毛布を提供を行いました。おかげで大勢の人が安全に夜を明かすことができたのです。そのような対応ができたのは、日ごろから危機管理の意識が高く、充分な備えがあったからです。
充分な水や保存食の蓄えの他、2005年からは事業継続計画の一環として、大規模災害時のマニュアル作りが行われていたのです。このマニュアルは「迅速に行動する」などの抽象的な表現では無く、「誰がどこの扉を開ける」など、かなり具体的な行動が書かれているそうです。
そしてマニュアルを作っただけでなく、定期的な避難訓練も昔から継続して実施していたそうです。実際の地震では、発生から数分後には総支配人を責任者とした現場指揮所が設置され、従業員に的確な指示を出すことができたのです。
こうした備えが功を奏し、大切なお客様と大切な従業員、そしてこれから大切なお客様になってくれるかもしれない人を守ったのですね。
悪い事例
こちらはホテルの話ではなく、デパートでの出来事です。1970年代、デパートで発生した火災により、死者118名、負傷者81名の被害が出ました。出火の原因についてはタバコの不始末と推定されものの、証拠不十分で不明とされました。
ですが、火災の備えが不十分だったせいで大惨事になってしまったことは、間違いないでしょう。特に犠牲者が多かったのはデパートに入居していた飲食店で、デパート側と非常時の連絡体制をどうするのか決めていなかったため、飲食店へ火災発生の連絡が行かなかったそうです。
この飲食店はデパートの防火管理責任組織、自衛消防隊組織に含まれておらず、共同防火管理や共同避難の意識が欠如していたとも言われています。避難誘導をする人もおらず、火災に気が付いた人がパニック状態に陥ったことも、被害拡大の原因のひとつです。
また、出火当時は防火シャッターも閉じられておらず火のまわりが早くなり、スプリンクラーも設置されていなかったそうです。設備の不備と、災害に対する日ごろの連携不足が重なって広がった被害ですね。
ホテルの危機対策で押さえておきたいポイント

iStock.com/mixetto
ここではホテルの危機管理全般において押さえておきたいポイントを説明します。
責任者を立て、円滑なコミュニケーションを取る
被害を最小限に食い止められるか、拡大するかは、ここにかかっていると言っても過言ではありません。災害時に誰の指示に従うべきか、連絡手段はどうするか、避難経路や集合場所について話し合う機会を設けましょう。
日ごろからの円滑なコミュニケーションは、従業員の不祥事を防ぐことにも効果があります。
言葉の分らない外国人のお客様への対応
ホテルには、外国人のお客様も大勢いらっしゃいます。東日本大震災で素晴らしい対応ができたホテルでは、お客様への呼びかけを英語と日本語で行ったそうです。
また、英語が通じない国からのお客様に向けて、簡潔なイラストで指示を出すなどの工夫も必要ですね。
ケガや病気で病院に運ばれたお客様の対応
火災や地震などが原因のケガでホテルから病院へ搬送される場合、お財布を持っていないことがあります。その場合の医療費の支払いや、保険会社への連絡をどうするかも決めておく必要があります。
風評被害対策
風評被害の対策も、危機管理の一環です。防ぐためには可能な限り現場に赴き、現状を確かめることが大切です。
そして、テレビやラジオの報道を確認し、事実では無いことが伝えられていればホームページに告知を出したり、可能であれば記者会見などでその旨を説明するという手段があります。
帰宅、帰国支援
お客様や従業員に安全に帰ってもらうことも、危機管理の重要な項目です。公共交通機関の運行状況お客様に案内したり、運行している電車がある駅までの送迎を行うことがあります。
こういった案内も、言葉の分らない外国人のお客様の案内に苦慮するかもしれません。あらかじめ、イラストや各国の言語で数種類の質問・回答が書かれたボードや翻訳機など、コミュニケーションツールを用意しておくと役に立つでしょう。
日ごろから必要な備え
どのような災害でも必要となるのは責任をもって指揮を取る人を決めておくことと、円滑なコミュニケーションです。日常から危機管理について話し合うことで、いざという時の心の準備にもなります。特に避難経路と避難計画を話し合うことは重要です。
そして、帰宅困難になりそうな人数を想定し、間に合うだけの物資を蓄えておきましょう。
お客様と従業員の安全を守るために

stockcom/AndreyPopov
安全な設備や備蓄も危機管理に欠かせない要素ですが、まずは災害時にどういった行動を取ればよいかを日ごろから話し合い、全従業員で共有することが大切ですね。
デパートの事例のような痛ましい災害が起こらないように、しっかりと危機管理を行いましょう。






 Facebookでシェア
Facebookでシェア X(Twitter)で投稿
X(Twitter)で投稿