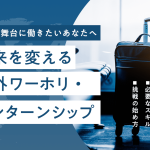飲食店の調理師や料理人の方のなかには、「自分のメニューをグランドメニューに載せたい」「味には自信があるのに、なぜか企画が通らない」と悩んでいる方もいるかもしれません。
その壁を乗り越えるカギは、味の追求だけではありません。お客さまのニーズや、利益を確保するコスト計算、競合との差別化を図るコンセプト設計といった経営視点です。
この記事では、調理師や料理人の方がキャリアを加速させるために、飲食店のメニュー開発に必要な論理的かつ実践的な7つのステップを体系的に解説します。
トレンド分析から、写真・ネーミングで注文率を上げる具体的なノウハウまで、開発スキルを正当に評価してくれる次のキャリアにつなげるための全ロジックを紹介します。
飲食店メニュー開発のカギは「味」ではなく「数字」
メニュー開発は、単にレシピを作ることではなく、店舗の売上やブランド、そして料理人の評価を左右する「経営戦略」そのものです。
どれだけおいしい商品を開発しても、それが数字で語れなければ、経営層や料理長を説得することはできないでしょう。
「数字で語る」スキルは、セカンドシェフからエグゼクティブシェフへの昇格や、将来的な独立を目指すうえで不可欠なビジネススキルです。
この意識をもつことが、飲食店のメニュー開発を「自己満足」から「売上貢献」へと変える第一歩となります。

宿泊業界に詳しいアドバイザーが、あなたに合う職場をいっしょにお探しします。
宿泊業界での職務経験はありますか?
飲食店メニュー開発の全貌が分かる!成果を出すための7ステップ
 78art / stock.adobe.com
78art / stock.adobe.com
メニュー開発を成功させるには、確固たるロジックに基づいた一連の流れを体系的に理解し、実行することが重要です。
以下の7つのステップを通じて、経営層に響く提案力を身につけ、売上に直結するメニュー開発へと進化させましょう。
- 失敗しないためのコンセプトとターゲットを定める
- 市場のニーズを確実に掴むトレンドと競合を分析する
- 開発目標と数値計画を確立する
- 売れる看板メニューを具体的に設計する
- 料理の価値を最大限に高めるメニューブックを構成する
- 試作と改善の科学的サイクルで成功確率を上げる
- データに基づき効果測定と見直しを行う
STEP1.失敗しないためのコンセプトとターゲットを定める
メニュー開発の最初のステップは、闇雲にアイデアを出すことではありません。
誰に、どんな価値を提供し、競合とどう差別化するかという核(コンセプト)を定めることが、成功の土台となります。
「誰に」届けるか?ターゲットの深掘り方法
まずは、ターゲットとする顧客を深く掘り下げることが重要です。
- ターゲットの年齢層、性別、ライフスタイル
- 来店ニーズ(例:記念日利用、日常のランチ、季節の味を楽しむ)
- 支払いにかけられる客単価のレンジ
これらを具体的に設定し、理想の顧客像を設定することで、メニューの価格帯や構成、ネーミングの方向性が決まります。
競合との差別化を実現するコンセプトの作り方
飲食店のコンセプトは、メニュー構成、価格帯、食材選定すべてを決定づけます。
「自店の強み」と「ターゲットのニーズ」が重なる部分こそが、競合と明確な差別化を図れるカギです。
たとえば、「地元の季節の食材を使ったヘルシーメニュー」というコンセプトなら、提供する商品やレシピ、空間のすべてをそこに結びつけましょう。
STEP2.市場のニーズを確実に掴むトレンドと競合を分析する
自分の作りたいものと、お客さまが求めるもの(ニーズ)の間にあるギャップを埋めるのが、この分析ステップです。
市場の動きと競合の動向から、メニューのヒントを抽出しましょう。
競合のメニュー構成から「売れ筋」と「抜け」を見つける方法
競合分析では、単に「何を提供しているか」だけでなく、「数字」を軸に差別化する視点が欠かせません。
たとえば、以下のような点をチェックするとよいでしょう。
- 客単価の比較:競合店の平均客単価やメニュー価格帯のレンジを把握する
- 看板メニューと季節限定メニューの分析:競合がどの商品で集客し、どの商品で利益を得ているかを推測する
- トレンドと「空白地帯」の発見:SNSや業界ニュースでトレンドを収集し、競合がまだ手をつけていない顧客ニーズの「抜け」を見つける(例:周辺にない、地食材を使った高級志向のテイクアウト商品など)
今、顧客が求めている「ニーズ」と「トレンド」の見極め方
SNSやデータ分析ツールを使い、トレンド情報を収集することも忘れてはいけません。
特に「季節」や「期間限定」のワードは、顧客の来店動機に直結するため重要です。
たとえば、「健康志向」「環境配慮型食材」「SNS映えするビジュアル」といった大きなトレンドは、メニューのコンセプトに深く関わってきます。
STEP3.開発目標と数値計画を確立する
料理人の技術を経営に直結させるのが数値計画です。売上と利益の目標を定め、それを達成するための具体的な原価率を設定します。
確実に「利益」を確保するための理想的な原価率の計算式
飲食店の原価率は、一般的に30%程度が目安とされています。
しかし、これはあくまで目安であり、利益を確保するためには、以下の計算式に基づき、目標の粗利率から逆算した販売価格設定のロジックが必要です。
原価率(%) = 原価 ÷ 販売価格 × 100
たとえば、一般的に粗利率の目安は65~70%程度とされるため、原価率は30~35%を目指すのが妥当なラインといえるでしょう。
原価率が低いドリンクメニューやサイドメニューと、原価率が高くなりがちな看板メニューのバランス(売上構成比)を考えることが、全体の利益率を確保するカギとなります。
「客単価」アップに直結するメニュー開発の考え方
客単価を上げるには、セットメニューやアップセル(上位商品)、クロスセル(関連商品)を組み込んだ構成を意識します。
たとえば、以下のような構成が挙げられます。
- メインメニューに、低コスト高利益の季節限定デザートやドリンクを「+300円」で追加できるセットメニューの提案
- メニューブックでもっとも目立つ位置に、客単価の高いコースメニューを配置
「メニュー開発費用」を抑え、ROIを高めるための工夫
試作段階で発生する新規食材の仕入れコストや、試作にかかる時間・材料費を予算化し、費用対効果(ROI)を高める考え方を身につけます。
既存食材の多用途化や、仕込み工数を抑えるレシピ設計を意識しましょう。
STEP4.売れる看板メニューを具体的に設計する
いくらおいしい料理でも、注文されなければ意味がありません。
このステップでは、味だけでなく、五感と心理に訴えかけ、集客に貢献する「看板商品」としての設計を学びましょう。
注文率を高める看板商品の4つの役割
看板メニューは、集客と売上に大きく貢献する、重要な「商品」です。以下の4つの点を意識してみましょう。
- 集客:SNS映えや話題性で来店動機をつくる
- 利益貢献:適切な原価率で利益を生む
- ブランドイメージ形成:お店のコンセプトを体現する
- 回転率向上:提供時間が短く、オペレーションがスムーズ
「写真」と「ネーミング」で価値を最大化する心理テクニック
魅力的なメニュー写真は、以下の3つのポイントをおさえて撮りましょう。
- 盛り付けの「高さ」を意識し、立体感を出す
- 自然光(太陽光)など、光の当て方で食材の新鮮さやツヤを強調する
- 料理以外の余分なものを写し込まず、商品に焦点を絞る
また、ネーミングには以下の2点を意識することが重要です。
- 食材の希少性や生産地を明記し、高級感を演出する(例:「○○産地直送」、「無農薬」)
- 「とろける」「芳醇な香り」など、食感や風味を連想させる形容詞を用いる
これらによって、看板メニューがフックとなり、SNSでの拡散を通じて集客に大きく貢献できるでしょう。
STEP5.料理の価値を最大限に高めるメニューブックを構成する
メニューブックは単なるリストではなく、最高の営業ツールです。顧客の行動心理を理解し、見せ方で客単価と満足度を同時に高めます。
客の視線を集め、高単価メニューに誘導する構成にはある法則があります。
それはZの法則(視線移動)といい、顧客の視線は横書きの場合、「左上」→「右上」→「左下」→「右下」とZの字に動く傾向があるというものです。
このことから、もっとも利益率が高く、客単価を上げるメニューを左上や右上のゴールデンゾーンに配置するとよいでしょう。
また、意図的に高額なメニューをメニューブックの目立つ位置に載せ、ほかのメニューを相対的に安く感じさせる、アンカープライシングという手法も有効です。
STEP6.試作と改善の科学的サイクルで成功確率を上げる
試作は感覚だけでなく、論理的に行うことで効率が劇的に向上します。標準化と効率化を意識したレシピ作成と、客観的な評価方法を確立しましょう。
レシピを標準化するには、誰でも再現可能な品質を保つ方法が重要です。
レシピは、「誰が作っても同じ品質」を実現するための設計図。分量や加熱時間、工程をすべて数値化し、感覚的な表現を排除します。
食材のカットサイズ(mm単位)や仕込みの時間、温度管理(℃単位)など、属人化を防ぐ具体的な情報も明記しましょう。
仕込みや調理工程をシンプル化し、現場のオペレーション負荷を最小限に抑えることも忘れてはいけません。
STEP7.データに基づき効果測定と見直しを行う
メニュー開発はリリースがゴールではありません。改善サイクル例(PDCA)を回し、常に最適化を図ることで、初めて長期的な売上貢献が実現します。
まずは、ABC分析でメニューの貢献度を把握する具体的な手順を把握しましょう。
リリース後のメニューは、データ分析により売上への貢献度を評価します。特に、ABC分析は、メニューを「継続」「改善」「廃止」の経営判断を下すために有効です。
<Aランク(重要メニュー)>売上高や利益貢献度が非常に高い商品。維持・強化策を講じる
<Bランク(準重要メニュー)>売上高はそこそこだが、集客や客単価アップに貢献している商品。改善によりAランクを目指す
<Cランク(低貢献メニュー)>売上・利益貢献度が低い商品。レシピやネーミングの変更、または廃止を検討する
販売数、売上高、利益率の3軸でメニューを定期的に評価し、継続的な改善を行う経営的な視点をもつことが重要です。
\開発スキルを最大限に活かす/
宿泊業界特化の無料転職相談に登録する今すぐできる!成果を出すための実践ノウハウ3選
 koumaru / stock.adobe.com
koumaru / stock.adobe.com
以上の7つのステップの理論を現場で活かすため、ここでは特に経験の浅い若手料理人でもすぐに取り組める、実践的なノウハウを3つに絞って解説します。
1.コストを抑えつつ、魅力を落とさない試作の技術
メニュー開発の費用を抑えるには、新規食材の仕入れを最小限にすることが基本です。
以下の点に注目しましょう。
- 既存食材の有効活用:すでに仕入れている食材の端材や規格外品を、ソースやサブメニューに活用できないかを考える
- 低コスト食材の格上げ演出:調理工程の工夫(低温調理など)や、盛り付けの美しさ、ネーミングで、低コストの食材を魅力的に見せる
- オペレーションコスト削減:レシピを極力シンプルにし、仕込みと調理にかかる人件費を削減する
2.承認を勝ち取るための「数字で語る」提案資料の作り方
料理長や経営層は「おいしい」だけでなく「利益が出るか」でメニューを判断します。
提案資料には、原価率、見込み売上、ターゲット層への訴求ポイントなど、経営層の関心事に基づいた具体的な数字を盛り込むことが重要です。
資料に含めるべき要素には以下のようなものが挙げられます。
- 新メニュー導入の背景(トレンド、顧客ニーズ、競合差別化)
- 数値計画(想定原価率、目標客単価、見込み売上)
- オペレーション負荷(調理時間の変化、必要な機材・人員の有無)
3.コンセプトがブレないためのメニュー構成の「型」を定める
コンセプトがブレると、メニューブック全体に一貫性がなくなり、顧客を混乱させます。
メイン、サイド、デザートの役割を明確にし、すべてのメニューがコンセプトに沿っているかを、開発途中で常にチェックする仕組みを作りましょう。
たとえば、「ヘルシー」がコンセプトなら、デザートにも低カロリーや自然な甘さといった要素を取り入れるべきでしょう。
\スキルと経験を評価してくれる職場へ/
プロの添削・面接対策を受ける飲食店のメニュー開発でプロが必ず守るべき3つの注意点
 jd-photodesign / stock.adobe.com
jd-photodesign / stock.adobe.com
メニュー開発の成功確率を高めるには、成功ノウハウを知ることと同じくらい、プロが「絶対にしてはいけないこと」を理解しておくことが重要です。
現場で陥りやすい3つの注意点を解説します。
1.自分の「作りたいもの」が先行し、市場のニーズを見失わない
個人の趣味や技術偏重、自分がおいしいと思うものだけを追求するのは危険です。
メニュー開発は、「お客さまが求めているもの(ニーズ)」と「お店のコンセプト」を満たす範囲内で行いましょう。
どれだけ高度な技術を要するレシピでも、顧客のニーズから外れていれば売上にはつながりません。常に市場のトレンドや顧客の声を優先することが重要です。
2.ポーション(量)とオペレーション負荷を甘く見積もらない
試作段階でおいしいと感じたとしても、実際に提供するポーション(量)での原価率維持、そして現場の調理スタッフが無理なく提供できるオペレーションレベルが確認できていないと意味がありません。
特に、新しいレシピを導入する際は、調理時間や必要な仕込みの手間、調理器具の占有時間を綿密にチェックし、提供時間が遅延しないかを検証することが重要です。
3.一度に多くの商品を開発して、質と改善サイクルを崩さない
質より量を優先すると、一つひとつのメニューの改善が遅れ、PDCAサイクルが回らなくなるリスクが高まります。
まずは看板メニューを少数に絞り込み、データ分析(ABC分析など)に基づいて徹底的に改善を図る方が、結果的に売上への貢献度が高まる傾向があります。
\「作りたいもの」を実現する!/
キャリアプランをいっしょに設計してもらう飲食店のメニュー開発に関するよくある質問
 ponta1414 / stock.adobe.com
ponta1414 / stock.adobe.com
ここでは、メニュー開発に携わる方々が抱えるキャリアの展望や、現場で直面しがちなコストや集客に関する具体的な課題について、Q&A形式で解消していきます。
メニュー開発は、将来的にどんな仕事につながりますか?
試作段階でコストを抑えるにはどうすればいいですか?
開発時に、SNS映えはどこまで意識すべきでしょうか?
\自分の開発スキルを磨く!/
専門チームに無料面談を依頼する飲食店のメニュー開発を通して、理想のキャリアを築こう
今回は、客単価と利益を最大化するロジックに基づいた、飲食店のメニュー開発7ステップを解説しました。
メニュー開発は、料理人としてのスキルと経営者としてのビジネス視点を統合する、キャリアアップのもっとも重要な業務のひとつといえます。
「数字で語る」スキルを身につければ、自分のアイデアが理想のキャリアを切り開く武器となるでしょう。
もし、今の職場で自分の開発スキルや経営視点が正当に評価されていない、あるいは、次のステップに進むための具体的な道筋が見えないとお悩みであれば、調理師専門の転職サイト「FURUMAU」の専門サポートを活用してみてはいかがでしょう。
一流レストランやホテルなど、ここだけの特別な求人もご紹介。あなたの経験や志向に寄り添い、ぴったりの職場をいっしょに探します。
\調理師専門の転職サポートはこちら/
FURUMAUで自分にぴったりの求人を探す






 Facebookでシェア
Facebookでシェア X(Twitter)で投稿
X(Twitter)で投稿