「住民税」「市民税」「県民税」という言葉を聞いて、「それぞれ違うものなの?」「何がどう違うの?」と疑問に感じていませんか?
特に、転職や退職を控えている方は、「会社を辞めたら支払いはどうなるんだろう?」と不安を感じているかもしれません。
これまでは給与から特別徴収で自動的に引かれていた税金が、自分で納付書を使って手続きをするのか、気になる方もいるでしょう。
実は、住民税・市民税・県民税は「同じ税金」を指しています。そして、その金額は、あなたの年収や確定申告の内容によって決まる「所得割」と「均等割」という2つの要素で構成されています。
この記事では、住民税の仕組みから、退職後の支払い方法、そして税金を安くする方法まで、あなたが抱える具体的な疑問を一つひとつ解消します。
税金に関する疑問や不安を解決し、自信をもって新しいキャリアの一歩を踏み出しましょう。
住民税・市民税・県民税は「同じ」!仕組みを最初に理解しよう
「住民税」「市民税」「県民税」という言葉を聞いて、「それぞれ違うものなの?」「何がどう違うの?」と疑問に感じていませんか?
実は、これらは「同じ税金」を指しており、<住民税 = 市民税 + 県民税>というシンプルな成り立ちになっています。
住民税とは、あなたが住んでいる地方自治体(都道府県や市町村)に納める税金のことで、行政サービスを維持するために使われる、地域社会を支えるための重要な税金です。
市民税は市町村に、県民税は都道府県に納める税金です。これらは、原則として会社が給与から天引きし、まとめて自治体に納めるため、給与明細には「住民税」としてひとつの金額が記載されていることが一般的です。
分けて表示されている理由は、それぞれの税金が納められる先(市町村と都道府県)と、使途が異なるためです。
しかし、会社員の方が支払いを気にする手続き上は、基本的にひとつの住民税として扱われます。

宿泊業界に詳しいアドバイザーが、あなたに合う職場をいっしょにお探しします。
宿泊業界での職務経験はありますか?
住民税は「2つの種類」で決まる!所得割と均等割の違いとは
 Trickster / stock.adobe.com
Trickster / stock.adobe.com
住民税は、大きく分けて「所得割」と「均等割」という2つの種類で構成されています。この仕組みを理解することが、住民税の金額を把握する第一歩です。
以下の表は、所得割と均等割について分かりやすく整理したものです。
| 項目 | 所得割 | 均等割 |
|---|---|---|
| 定義 | 前年の所得に応じて決まる税金 | 所得に関係なく一律で課税される税金 |
| 税率/金額 | 一律10% | 一律5,000円 |
| 内訳 | 市民税:6%/県民税:4% | 市民税:3,500円/県民税:1,500円 |
| 備考 | 控除などにより変動する | 森林環境税の導入により、金額が変更される可能性がある |
年収で決まる「所得割」は所得の10%
所得割とは、前年1月1日から12月31日までの所得(年収から経費などを引いたもの)に応じて金額が決まる税金です。
所得割の税率は、原則として全国一律で10%と定められています。この内訳は、市民税が6%、県民税が4%です。
所得割は、保険料控除や扶養控除など控除の手続きを行うことで課税対象となる所得が減り、支払い金額が安くなる仕組みになっています。
年収に関係なく決まる「均等割」は一律5,000円
均等割とは、所得の金額に関係なく、住民税の支払い能力があると認められる方に一律で課税される税金です。
標準税額は、市民税が3,500円、県民税が1,500円の合計5,000円です。これは、地方自治体の提供する、ごみ処理や消防などの均一的なサービス費用を、広く公平に負担するためのものです。
なお、2024年度から「森林環境税」(年額1,000円)が均等割に加算されており、これによって今後の均等割の金額が変更される可能性があることにも注意が必要でしょう。
【転職者必見】住民税の「支払い方法」は2種類!損をしない選び方
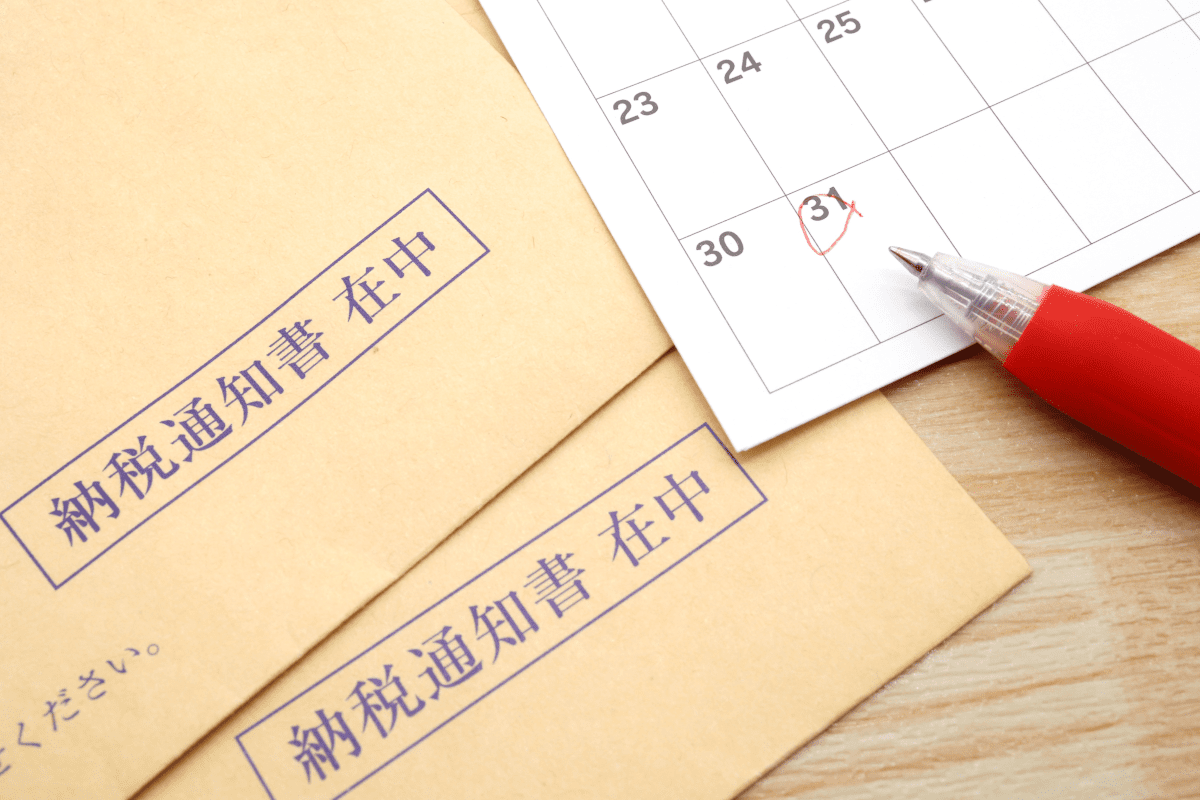 umaruchan4678 / stock.adobe.com
umaruchan4678 / stock.adobe.com
会社員の場合、住民税が給与から天引きされているはずです。しかし、転職や退職をすると、この支払い方法が変わり、手続きが必要になる可能性があります。
住民税の主な支払い方法には、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。
会社が給料から天引きする「特別徴収」の仕組み
「特別徴収」とは、会社(給与支払い者)が従業員の毎月の給与から住民税を天引きし、まとめて自治体へ納付する仕組みです。会社員の方のほとんどは、この特別徴収で支払いをしています。
この仕組みのメリットは、自分で納付手続きをする手間がなく、納め忘れの心配もないことです。
デメリットとしては、給与から自動的に天引きされるため、毎月の手取り額がその分減ってしまうことが挙げられるでしょう。
自分で納付書で支払う「普通徴収」の仕組み
「普通徴収」とは、地方自治体から送られてくる納付書を使って、自分で金融機関やコンビニなどで住民税を納付する仕組みです。年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて支払いをするのが一般的です。
給与から天引きされなくなるため、手取り額はその分増え、自分で納付のタイミングを管理できます。しかし、納付書が届いたあとの支払い忘れや、納期限を過ぎた場合の延滞金の発生には注意が必要です。
退職や転職によって、普通徴収に切り替わると、納付書が自宅に届くことになります。
納付書がいつ頃、どこから届くかについては、記事後半のよくある質問でも詳しく解説しています。
また、住民税を普通徴収に切り替えた場合の納付書での支払い手続きについて、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事もぜひご覧ください。
転職時の住民税は「一括徴収」か「普通徴収」になる
退職によって給与からの特別徴収ができなくなると、住民税の支払い方法が変わります。これは、退職する時期(月)によって手続きが異なるためです。
以下の表から、どちらの支払い方法になるのか確認しておきましょう。
| 退職月 | 徴収方式 | 最後の給与からの天引き |
|---|---|---|
| 6月〜12月 | 普通徴収への切り替え | 退職月までの住民税は天引き 残りは普通徴収(納付書)で自分で支払い |
| 1月〜5月 | 一括徴収が原則 | 退職月から5月までの住民税が最後の給与から一括で天引きされる |
なお、退職と同時にすぐに新しい会社に転職する場合は、新しい会社に特別徴収を引き継ぐ手続きが可能です。この場合、自分で支払い手続きをする必要はありません。
また、1月〜5月に退職する場合は、最後の給与や退職金から5月分までの住民税が一括で天引きされるため、退職月の手取り額が大幅に少なくなる傾向があります。
「退職月は手取りが少ない」という話を聞くのは、この一括徴収が原因の場合が多いです。
退職時に会社側へ「普通徴収に切り替えたい」と申し出をすれば、一括徴収を避けられる場合もありますが、会社の手続き状況や自治体の規定によって異なるため、必ず退職前に担当部署に確認しておきましょう。
転職や退職に伴う税金や社会保険の手続きについては、こちらの記事で全体像を解説しています。
\税金から面接まで安心!/
プロのサポートで転職を成功させる住民税を安くする方法はある?「控除」と「ふるさと納税」の活用法
 aijiro / stock.adobe.com
aijiro / stock.adobe.com
住民税の金額は、年収だけでなく、「控除」や「ふるさと納税」といった制度を活用することで安くできます。ここでは、その具体的な方法を解説します。
控除を活用して住民税を減らす仕組み
所得控除とは、年収から所得割を計算する際、所得金額を減らすことができる仕組みです。所得が減れば、課税される住民税(所得割)の金額も当然安くなります。
代表的な控除には、以下のようなものがあります。
<社会保険料控除> 健康保険料や厚生年金保険料など、支払いした社会保険料の全額
<生命保険料控除> 支払いした生命保険料の金額(上限あり)
<扶養控除> 養っている親族がいる場合
<医療費控除> 年収に応じて、多額の医療費を支払いした場合
会社員の場合、これらの控除は年末調整で手続きを済ませることが多いです。
しかし、退職した年は自分で確定申告を行うことで、控除を適用でき、住民税や所得税を安くできる場合があります。
「ふるさと納税」で住民税を控除する方法
ふるさと納税とは、全国の自治体へ寄附ができる制度です。個人の年収などに応じた、控除上限額までの寄附であれば、寄附した金額から2,000円を引いた全額が、所得税と住民税から控除・還付されます。
この上限額の範囲内であれば、実質2,000円の負担で、さまざまな返礼品を受け取ることができます。
転職や退職の状況で確定申告の手続きに不安がある方(もともと確定申告の必要がない給与所得者など)は、「ワンストップ特例制度」を利用すれば確定申告が不要になることを覚えておくとよいかもしれません。
ただし、この制度を利用するためには、ふるさと納税先の自治体が年間で5団体以内であるなどの要件があることにも注意が必要です。
控除やふるさと納税を最大限に活用し、支払いを最適化するための詳しい手続き方法はこちらの記事で紹介しています。
\専門的な悩みもプロに相談!/
ホテル業界に詳しい専門チームに相談する住民税・市民税・県民税に関するよくある質問
 christianchan / stock.adobe.com
christianchan / stock.adobe.com
退職や転職を控えていると、給与から引かれる住民税の扱いや、自分で納付が必要になるのかなど、税金の手続きで不安や疑問を感じることも多いのではないでしょうか。ここでは、転職者から寄せられるよくある質問とその答えを紹介します。
退職月の住民税は、なぜ給与から一括で引かれるのですか?
パートやアルバイトでも住民税はかかりますか?
住民税の納付書は、いつ頃、どこから届きますか?
2024年(令和6年)に実施された「定額減税」とは何ですか?
住民税が非課税になる年収の基準を教えて下さい。
\転職の不安、まとめて解消!/
無料相談で理想の転職を叶える 出典:地方税の仕組み/総務省 出典:個人住民税/総務省 出典:ふるさと納税ポータルサイト/総務省 出典:No.1100 所得控除のあらまし/国税庁住民税を理解して、「おもてなしHR」と不安なく理想の転職を叶えましょう
今回は、住民税・市民税・県民税は「同じ税金」であり、所得割と均等割の2種類で構成されていること、そして転職・退職の状況における支払い手続きの変更点について、詳しく解説しました。
税金の仕組みが明確になったことで、「知らないまま損をするかもしれない」という漠然とした不安が解消され、新しいキャリアへの見通しが立ったのではないでしょうか。
住民税の支払い手続きだけでなく、転職活動全般にも不安を感じているなら、ぜひ「おもてなしHR」の無料相談をご活用ください。
私たちおもてなしHRは、宿泊業界に特化したプロのキャリアアドバイザーです。
あなたのこれまでの経験を、おもてなしの現場でどのように活かせるかを具体的に言語化し、履歴書の作成や面接の相談にも乗ることで、不安なく理想の転職を叶えるための万全のサポートをいたします。
会社任せではなく、自分自身の力でお金や手続きの仕組みを理解できたという自信を胸に、おもてなしHRとともに、ワンランク上のキャリアを目指しましょう。
\あなたの強みを見つけてくれる!/
おもてなしHRに無料登録する

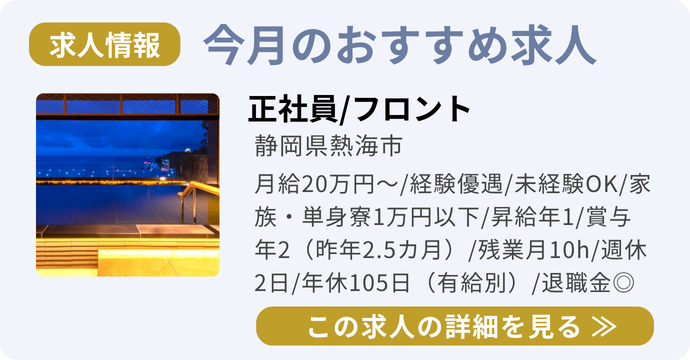
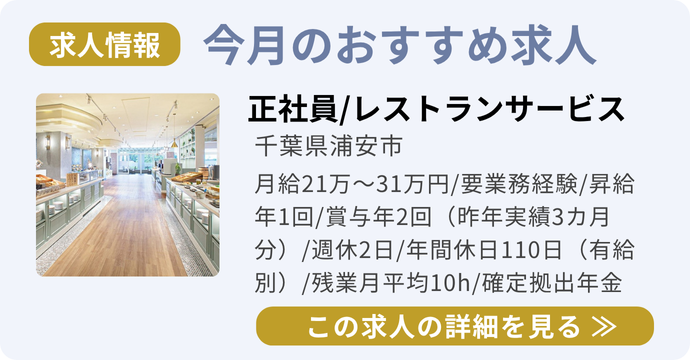
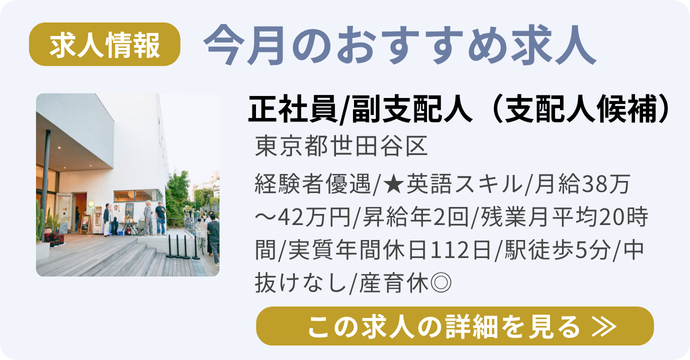
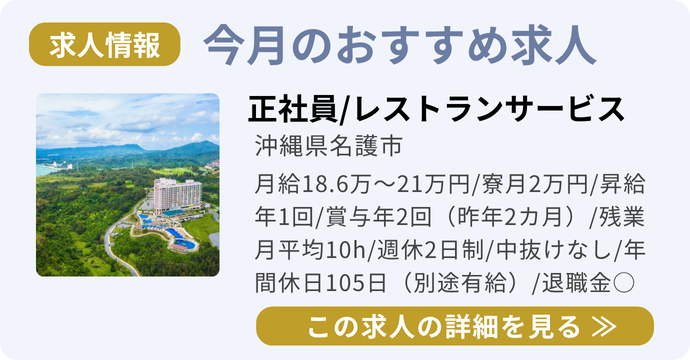
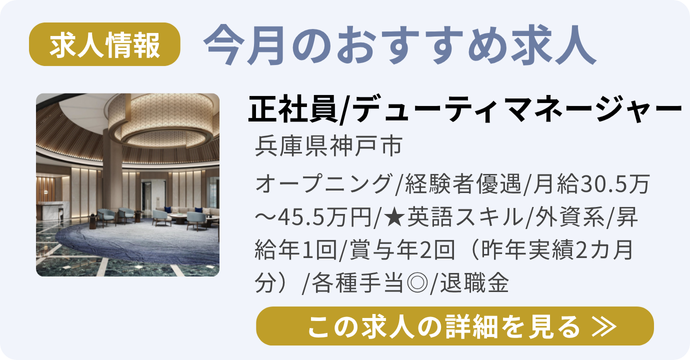
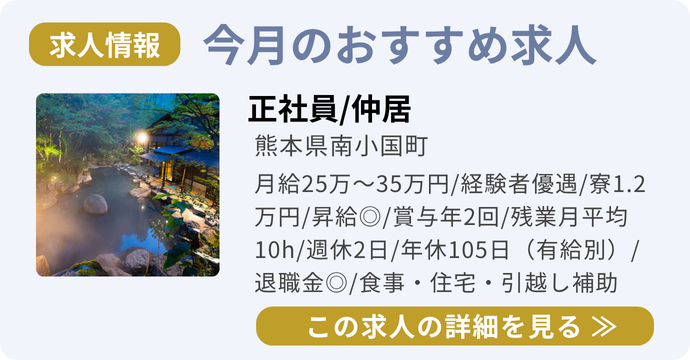
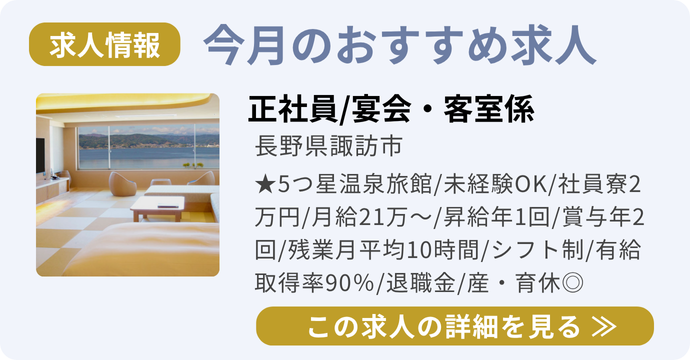
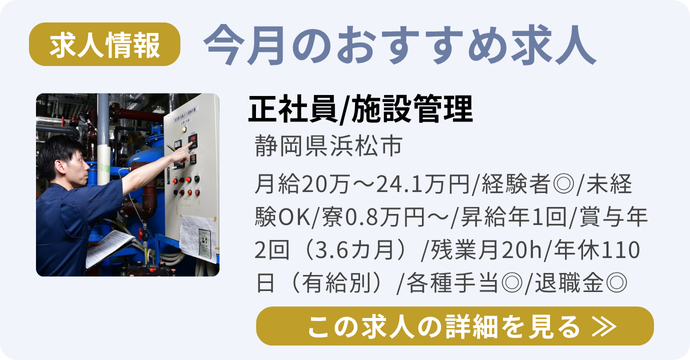
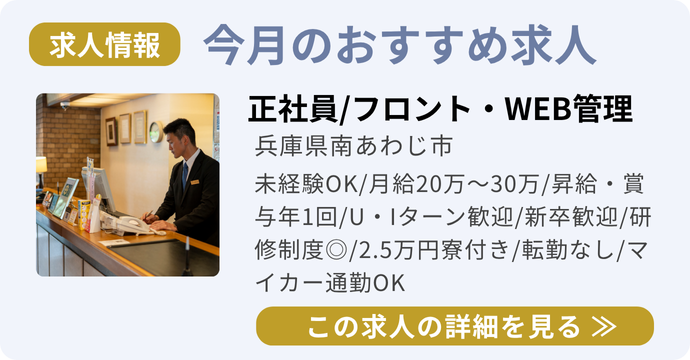
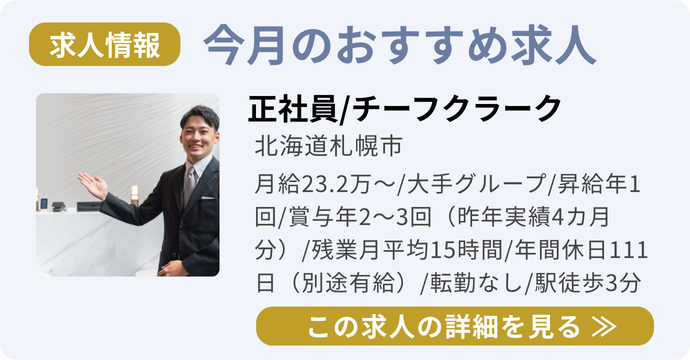
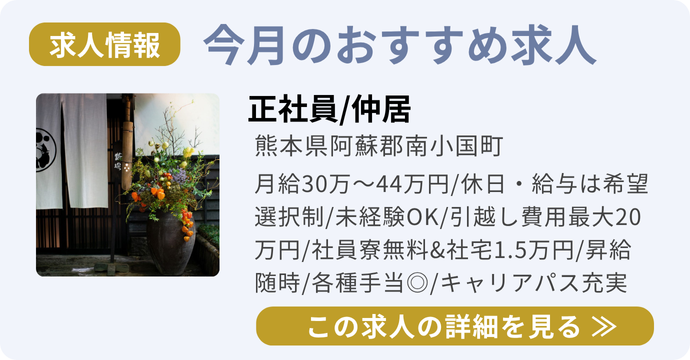
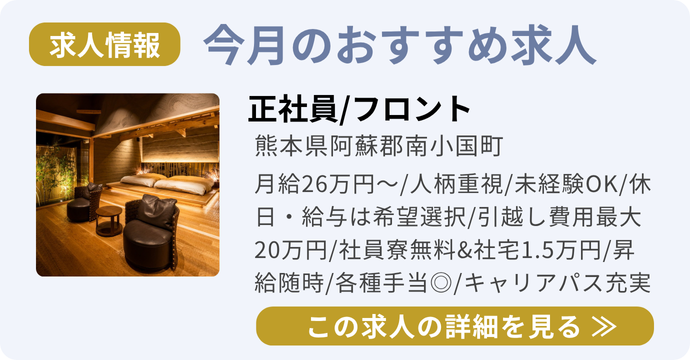
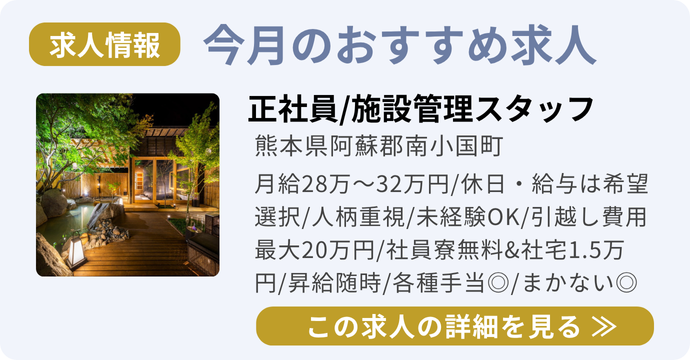
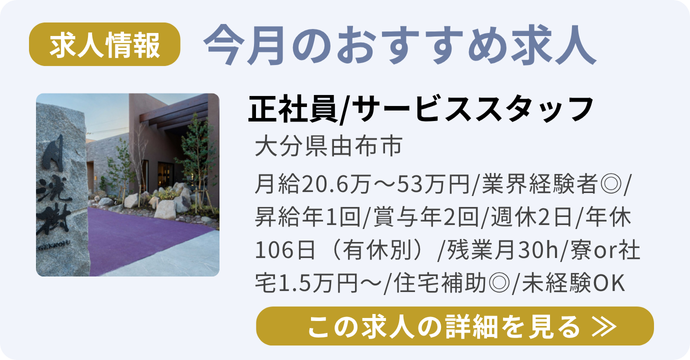
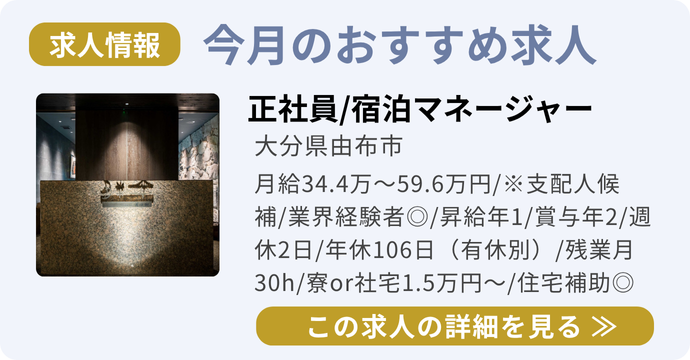
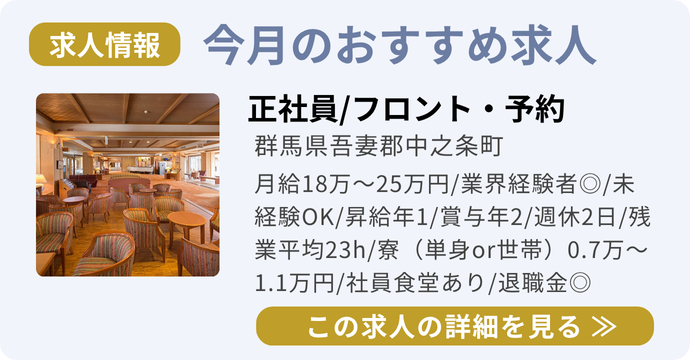
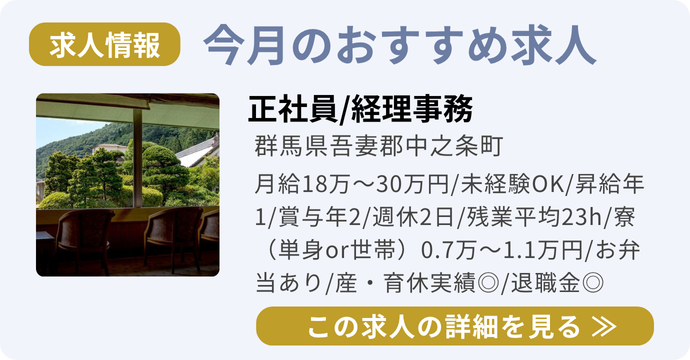


 Facebookでシェア
Facebookでシェア X(Twitter)で投稿
X(Twitter)で投稿












































































































































