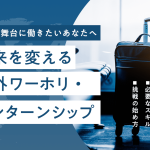ホテリエと聞くと、接客業の中でも特におもてなしに長けているイメージがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんなホテリエの中で一流と呼ばれる方々は、どのような部分に秀でているのでしょう。この記事では、ホテルオークラにて、約18年に渡り玄関、ロビーを担当するサービスのスペシャリストとして勤務、その後も社内サービスインストラクターとして、ホテルオークラでの30年間で約3000人の新人指導の実績をもつ蔵田理さんに、ホスピタリティ・マインドを中心としたお話をお伺いしました。
ホスピタリティ・マインドの正しい意味

―――ホスピタリティ・マインドとは、どういうものなのでしょうか?
よく勘違いされがちですが、”ホスピタリティ”と”サービス”は同じものではありません。
「ホスピタリティ・マインド」という言葉にあるように、大事なのはマインド。つまり、相手への思いや気持ちを行動として具現化することです。
似た言葉で”ハート”がありますが、ハートとマインドは、また異なるものです。ハートというのは「思い・気持ち」のことで、例えば、杖をついた年配の方が電車に乗ってきた場合「席を譲ろうかな」という気持ちを持つことを指します。
その気持ちを具現化して、実際に席を譲る行動を起こすことを、マインドと呼ぶのです。
繰り返しにはなりますが、ホスピタリティ・マインドとは具現化して行動することなのです。
ホスピタリティとサービスは全く異なる
―――ホスピタリティとサービスの違いについて教えてください。
まず語源が異なります。ホスピタリティは、ラテン語の「hospes(ホスペス)」に由来しているといわれています。
中世時代、ヨーロッパにはまだ宿が存在していなかったので、教会が、旅人や兵士に「hospes(ホスペス)」と呼ばれる宿のような場所を、提供していました。”利害関係がないおもてなし”というわけです。
教会が損得を考えず、相手の「こうしてほしい」「こうしてくれたら嬉しい」を伺い、ホスペスの提供を始めたことから、ホスピタリティは、求めていることを理解し、それに対して、具体的に行動を移すことを指すようになったのです。
一方、サービスをラテン語にすると「servus(セルウス)」という言葉に行き着きます。これは「奴隷」という意味ですね。
「奴隷」という言葉で思い浮かべるのは、上下関係、つまり縦の関係かと思います。したがって、サービスは相手に対して決まったこと、もしくは相手が求めるであろうことを事前に用意して提供することを指します。
このような背景から、サービスはマニュアルがあればできます。ですが、ホスピタリティはマニュアルを超えたところにあるのです。100人のお客様がいれば、100通りのおもてなしがある、それがホスピタリティです。
―――ホスピタリティ・マインドが備わっている方に特徴はありますか?
気づく・察知する目を養われている方が多いと思います。このようなことが得意な方は、元々性格的におせっかいということもあるかもしれませんが、ホテルマンとして経験を重ねることで、養われたのではないでしょうか。
相手の求めることを察知する能力は、意識をして訓練をすれば養うことができます。本来、おもてなし(御持て成し)というのは、「持って」「成し遂げる」ということなので、自分に足りないと思うのであれば、気持ちとして持っているだけではなく、行動して具現化しましょう。
ホスピタリティ・マインドを養う方法として、私は「おもてなしの五配り」を推奨しています。昔は「目配り・気配り・心配り」を指して、おもてなしの三配りと云っていました。
| 目配り | 気づく目を養うこと |
| 気配り | 気配を感じ取れること |
| 心配り | 相手を心配できること |
私は、ここに「耳配り・頭配り」の2つを足します。
耳配りは、お客様の些細な会話、何気ない一言もキャッチしてサービスの向上に繋げること、頭配りは、気づいたことやキャッチした情報を活かし、サービスをレベルアップさせることです。お客様の情報をキャッチしても、それをサービスのレベルアップに繋げていかなければ何にもなりませんので。
| 耳配り | 些細なことでも聞き逃さない |
| 頭配り | 得た情報をサービス向上に繋げる |
 pressmaster / stock.adobe.com
pressmaster / stock.adobe.com
コミュニケーションは言葉+所作で完成する
―――ホテリエに必要なコミュニケーション方法、コミュニケーション能力とはどのようなものでしょうか?
コミュニケーションの方法には、言語を使用したバーバルコミュニケーションと言葉以外で表すノンバーバルコミュニケーションの2つがあります。詳細な割合については諸説ありますが、人はノンバーバルコミュニケーションの方がより多くのことを伝えることができるといわれています。つまり、コミュニケーション能力=言葉だけではない、ということですね。
口先だけでなく、体全体で相手に思いを伝えていくことが重要です。バーバル、ノンバーバルの両方を駆使して伝えていきましょう。
―――2つを駆使するためにはどのようなことが必要でしょうか?
言葉と、それを表現する所作を身につけることが必要でしょう。私は、これを接客をする上での5つの心「明るい心、歓迎の心、素直な心、丁寧な心、感謝の心」と呼んでいます。
 one / stock.adobe.com
one / stock.adobe.com
例えば、明るい心について。「おはようございます」を明るく表現するには、どのように伝えればいいでしょうか。明るさを表現するのは「あ」の音なので、「おはようございます」の中にある「は」の音を少し明るくするだけで、受け手の印象は驚くほど変わります。つまり、音一つでも、接客をする上では意識すべきということです。
加えて、この「おはようございます」を、人を明るい気持ちにさせる所作である「笑顔」と一緒に伝えることで、コミュニケーションとして完成されます。
歓迎の心を表したいときは「いらっしゃいませ」とお辞儀を、素直な心を表現するときは「はい」という返事の言葉を伝える。
いずれの言葉も接客においてよく使われる言葉ですが、大切なことは、当たり前のことを当たり前にやることです。そのためには基本的なことをしっかり理解する必要があります。
| 言語例 | 非言語例 | |
| 明るい心 | おはようございます | 笑顔 |
| 歓迎の心 | いらっしゃいませ | お辞儀 |
| 素直な心 | 「はい」などの返事 | 正対(※)
手のひらを相手に向ける |
| 丁寧な心 | 丁寧語+センテンスで伝える | 両手で手渡し |
| 感謝の心 | ありがとうございます | 出迎え三歩、見送り五歩
笑顔 |
※相手に対して、骨盤を平行に向けること
感謝の心を伝えるノンバーバルコミュニケーションの例として、お客様を出迎えるときには三歩前に出て出迎えましょう、お見送りのときには二歩加えて五歩で見送りましょう、という「出迎え三歩、見送り五歩」というものがあります。
どういうことかというと、お出迎えのときには、これからお客様をおもてなしするチャンスがありますよね。一方、お見送りのときには、お客様が出発されるので、その先がありません。だから、二歩加えてしっかりこちらの思いを伝えて余韻が残るようなおもてなしにしましょうということです。
話が前後しますが、上記の中でも、特に「素直な心」が欠けているホテリエが増えていると感じます。
―――それは時代と共に、ホテルの接客マニュアルが変わってきているということなのでしょうか?
マニュアルもそうですが、指導をしていないという現状はあると思います。時代の移り変わりで、指導内容が変わるというのは当然あるので、今の時代にどこまで求めるのかというのが前提にありますが、やはり個人としては、おもてなしの在り方を変えてはいけないと思っています。
変わりゆく時代にあるからこそ、これまでと変わらないおもてなしができるホテリエであって欲しい。そのためには基本的なこと、当たり前のことが当たり前にできることが一番大切です。
海外のお客様だからこそ、日本の文化を伝える

―――現在(2025年3月)、インバウンドの需要で海外のお客様が増えています。海外のお客様に向けて、ホテリエとして基本的な心がけや、コミュニケーション方法などはありますか?
迎える側として、全てのお客様の母国語でお話ができれば、バーバルコミュニケーションとして、これ以上なことはありません。語学力はあるに越したことはないです。とはいえ、日本でおもてなしをするわけなので、綺麗美しい日本語を伝えることも大事だと思います。
また、海外のお客様を迎える際には、その国の文化を理解することが重要です。私が現役ホテルマンのときには、欧米のYES/NOをはっきり表現する文化に苦労した覚えがあります。特に日本語はグレーで曖昧な表現が多いので。ただ、全てに迎合する必要はないと思っています。日本である以上、日本の文化やあるべきルールを伝えることもおもてなしをする側としては必要でしょう。
ホテリエとして大切にしている心構え
―――最後に、蔵田さんがホテリエとして最も大切にしている心構えをお聞かせください。
「NOをいわない」ということです。これは私がサービスを提供する中で、最大のテーマですね。
もちろん、全てのことが出来るわけではありませんので、結果として承ることが出来ないこともあります。ですが、NOと言ってしまったらサービスは始まらないし、NOと言った時点でお客様との関係は絶たれてしまいますので、まずはYESと答えるようにしているのです。
仮に出来なかった場合も、二次提案、三次提案をすることで、お客様のご要望をそのまま承ることはできないけれど、「このようなお手伝いならすることができます。いかがでしょうか?」と提案してお客様との接点を見つけていきます。
様々なことを考えて、どのようにしたらお客様の思いを具現化してあげるのか、どのようなお手伝いができるのか、こういった気持ちがホテリエには大事なのではないでしょうか。


 Facebookでシェア
Facebookでシェア X(Twitter)で投稿
X(Twitter)で投稿